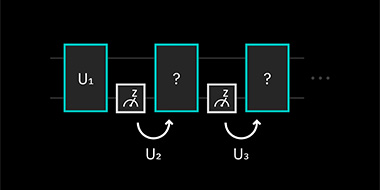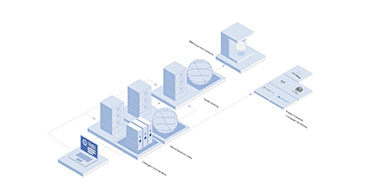Mugendai(無限大)
顔を思い浮かべて制度を作る。スープストックトーキョーの「働き方開拓」
2020年10月6日
カテゴリー Mugendai(無限大)
記事をシェアする:
飲食業界で働く社員のイメージといえば、長時間労働、少ない休日など、長らくマイナスなイメージで語られることが多かった。しかし、スープストックトーキョー(以下、SST)はそのイメージを根本から覆すような大胆な人事制度を打ち出し、社員の「生活価値拡充」を図っている。例えば「年間休日休暇120日」、「社員の複業OK」、「誰もが申請できる時短勤務」など、本当に実現可能なのかと思う驚きの施策が並ぶ。
そうした制度を形にして実現していったのが、アルバイトから社員になり、その後人材開発部の部長となった江澤身和氏。現在は副社長として同社の「働き方開拓」を推し進めている。SSTの理想的な人事制度は、いかにして生まれてきたのか。成功の秘密を紐解く。
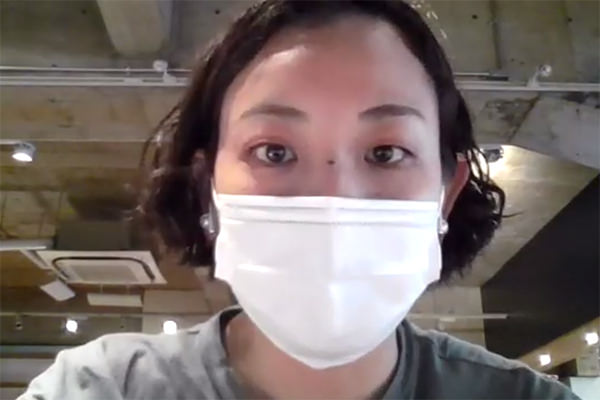
ビデオ通話にてインタビューを実施
目次

(えざわ・みわ)
株式会社スープストックトーキョー 取締役副社長 兼 店舗営業部部長
短大卒業後、2005年にパートナーとして入社。社員登用後、複数店舗の店長を歴任。その後、法人営業グループへ異動し、冷凍スープの専門店の業態立上げと17店舗の新店立上げを牽引。2016年2月、㈱スープストックトーキョーの分社に際し、取締役兼人材開発部部長に着任。 “人を大切にする”を基軸とした14の人事制度を展開し、本質的な採用・育成の仕組みづくりに取り組む。2018年12月、「Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2018」 において、チェンジメーカー賞を受賞。
きっかけは、友人の「スープストックトーキョーが好き」という言葉
──江澤さんは、はじめはパートナー(アルバイト)としてスープストックトーキョー(以下、SST)で働き始めたとのことですが、どんなところに魅力を感じて働き始めたのでしょうか?
江澤 短大を出てフリーターとして5年間ほどさまざまなアルバイトを経験しているときに、友人に誘われたのが、そもそものきっかけでした。なぜその誘いに乗ろうと思ったかというと、その友人はよく、「SSTが好きだ」と言っていたんですよね。いくら好きでも職場の内情を知ると少し熱が冷めたりするものだと思うのですが、働き続けてなお「好きだ」と言えるということは、その魅力が本物だからだと思ったんです。もちろん私自身もSSTのスープが好きで、お店の雰囲気も気に入っていたので、それなら働いてみようと。

──実際に働き始めて、SSTという会社にどんな印象を持ちましたか?
江澤 働いてみて思ったのは──これは私がその後、社員になったきっかけにも通ずることなのですが──まず、自分たちが提供する商品や店舗空間について、とてもこだわりの強い会社だなと。ひとつひとつ妥協なく、自分たちが納得いくものでなければ提供しないという姿勢がブランドを作っているのだと感じました。とは言え、私が入った当時はSSTも展開し始めて4〜5年くらいの時期で、まだまだ模索の時期でもありました。マニュアルやルール、教育のしくみなどが、良くも悪くも固まっていないという印象でしたね。
例えば、店内清掃一つとっても、うちの店舗ではこうやっているけど、他の店舗はまったく違うとか、その記録表のフォーマットも店舗ごとにバラバラだったり。もちろん商品のレシピは存在しますが、その他、入社後に覚えていくことのマニュアルのようなものは、私の記憶では存在していなくて(笑)。最低限のルールはありましたが、それも先輩から後輩へと教えていくという感じで、可視化されていなかったんです。
でもそれは裏を返せば、店長や店舗ごとの裁量で、お店を良くしていくための工夫ができるということでもあり、自分にとってはそこが魅力的に映りました。というのも、SSTで働く前のフリーター時代、たまたま旅行で訪れたゲストハウスがとても素敵で、そうした空間やコミュニティを作ることに興味を持ち始めていて。店舗運営やお店の経営に興味があったので、裁量を持って店舗でいろいろなことを決められるのは面白いなと思っていました。

従業員への「評価」は「こういう人になってほしい」というメッセージ
──その後、江澤さんは社員になるわけですが、どんなきっかけがあったのですか?
江澤 何人もの社員さんに「将来どうするの?」「どんなことを考えているの?」と聞かれて、さっき言ったような夢を語るたびに、「だったらうちで社員になればいいじゃない」と言われて、確かにそうだよなと(笑)。そこで初めて、“自分が社員だったら”という目でSSTを見るようになりました。その頃はちょうど会社自体がこれからどんどん新しいものを作っていこうというタイミングでもあり、ここで社員として働くことに興味を持ったんです。
そして社員になった後、複数の店舗で店長を歴任し、新店舗の立ち上げにも何度も携わっていくうちにSSTの改善すべきポイントとして見えてきたのが、社員やパートナーへの評価と教育です。自分自身が一社員として働く中で、“成長”と“評価”が一致しないと感じる場面や、“評価”と“教育”の連動ができていないと感じる場面がありました。評価軸が可視化されていないがゆえに、各上長によって評価のバラつきが出ていた。各店舗の個性が出るのは良いことだけれど、評価軸や教育方針は属人化してはいけない部分だと思っていました。
──その後、2016年、スマイルズからスープストックトーキョーが分社化するタイミングで、江澤さんは人材開発部の部長に就任されます。そこで最初に取り組まれたのはどんなことでしたか?
江澤 やはり、社員の評価制度を見直すことから始めました。その後にすぐパートナーの評価のしくみを作ることにも取り掛かって。評価は働く人に向けて「こういう人になってほしい」というメッセージでもあると思うんです。社員を評価する制度を可視化するということは、「私たちが求めている人物像はこういう人です」、「だからこういうことができるようになってくださいね」というメッセージになるものだと。私自身が、SSTは商品や店舗が持つブランド力だけでなく、働く“人”こそが大きな魅力だと常々感じていたので、もっとその部分をお客様にも伝えたいと思っていたんです。
その後『SSTグランプリ』という、社員とパートナーのための成果発表イベントを定期的に行うようにもしました。弊社には“世の中の体温をあげる”という理念があるのですが、さまざまな店舗でその理念を実現しようと努力している人たちがたくさんいて、その取り組みやエピソードを発表してもらうんです。例えばまだ学生であったり、アルバイトが初めてのパートナーさんが、お客様の体温を上げるために考えて動いたこと――そのエピソードを聞くのは感動的です。その取り組みが全社的にきちんと賞賛されるしくみを作ることで、みんなが日々の仕事に自信を持つ場面が増えていくし、理念が浸透していっていることも実感できるのです。

『SSTグランプリ』の様子
「年間休日休暇120日」「複業OK」etc. 驚きの「働き方開拓」
──御社は「働き方改革」ならぬ「働き方開拓」と銘打って、大胆な職場環境の変革や人事制度の制定を行なっています。例えば「年間休日休暇120日」というのは、飲食業界では驚きの休日数です。どのように実現してきたのでしょうか。
江澤 人材開発部として、各店の人員不足の解消は大きな課題でした。人員が不足していれば社員は休みを取れない。その疲弊から退職というマイナスの流れができつつあって、退職を希望する社員と面談する機会も増えていました。そうして辞めていく人たちが口々に言っていたのは、「SSTのブランドや働く人たちはすごく好き。でも休日が取りづらく、不規則な働き方が続くなら、働き続けるのは難しい」ということでした。飲食業はやりがいのある仕事だと思っているのに、拘束時間の問題で離れていく仲間がいることはもったいないし、悔しかったんです。“飲食業=ブラック企業”と一概に言われてしまうことも腹立たしく感じるし、イメージを変えたいと思いました。
年間休日休暇を120日と決めたのは、カレンダーの1年の休日が約120日だからです。なので、カレンダー通りに休むのは無理だとしても、同じ日数は休めるようにしようと。

年間休日休暇120日を目指す「生活価値拡充休暇」
──ルールを改定したとしても、実際にそれを有効的に運用するのは難しかったと思うのですが、どのように実現させていったのですか?
江澤 例えば、月間8日の休みを取ることを目標にしても、なかなか達成できなかったりします。なので、月間9日の休日、という少し高めの目標を定めて、それに向けて人員を採用し、教育を進めていきました。目標のハードルをひとつあげることで、実現に近づくと考えたんです。休日の日数を増やしても社員の給与は下げていないので、その分人件費は上がってしまうのですが、これを実現することで残業代は削減できます。残業が少なくなるということは、働く人の生活価値の拡充にもつながります。そうすることで社員になりたいと思う人も増える。
この循環を実現させるために“特殊部隊”を結成しました。どこの店舗にも属さない店長クラスの社員で結成しており、人員が足りなくて社員が休めないという店舗にヘルプで入ります。つまり「年間休日休暇120日」を実現させることを目的とした部隊を作って、社員がしっかり休みを取れるようにしました。
──ルールの制定と実現のための施策が必ずセットになっているところが素晴らしいと思います。もうひとつ、「ピボットワーク制度」、つまり「複業OK」というのも非常に驚きの制度だと思うのですが、これはどういった経緯でスタートしたのでしょうか。
江澤 これもまた、社員が退職していくときによく耳にした言葉なのですが、「SSTしか知らないので他の仕事を覗いてみたい」と。長く働いていた人ほど、その言葉を口にするのですが、違う分野に興味を持ったり、チャレンジしたくなったりするのはとても良いことなのに、会社を辞めなければそれができないというのは、なんだかもったいないなと感じていました。社員の平均年齢も30歳くらいで、将来の可能性をいろいろと考えている人も多いと思うので、在籍しながらいろいろな世界を見られるようにしたかったんです。

複業を認める「ピボットワーク制度」
──一方で、複業を認めると人材流出というリスクも負うことになると思うのですが、その点はどのように考えていましたか?
江澤 確かにその懸念は大いにありましたが、いろいろな世界に興味を持っている人や、チャレンジ精神のある人のほうが、私たちと働いてほしいと思う人物像に合致すると思ったんです。趣味の延長でいろいろなことに関わるのでもいいし、複業として始めるのでもいい。そのフットワークの軽さがSSTでの仕事にも活きるでしょうし、変に囲い込んでしまうより、会社にとってプラスになると考えています。実際に人材開発部としてこの制度の実現のために理解を得るのは大変でした。ですが、新卒採用の場面でも、時代の流れを感じながら、企業側が変わらなければいけないタイミングでしたし、こちらがどう腹をくくるかだと思って実現に踏み切りました。
女性が働きやすい会社は男性も働きやすい
──どうしたら、そのように思い切った人事制度を思いついて、実現させることができるのでしょうか。
江澤 どの制度もそうなんですが、基本的に「その制度を使ってほしい」と思う人の顔が浮かんだり、「こういう制度がなければこの人をサポートできないな」と思ったりするところから考え始めることが多いです。制度を作ったとしても、ひとりも使ってくれる人の顔が浮かばないのなら、いくら会社のブランドイメージを高めるものであってもまったく意味がないと思うので、導入時にはそれはいつも意識しています。

社員、パートナー、共通の3つの対象に向けて、「働き方」「エンゲージメント」「人材開発」の3軸で人事策を講じている
──女性の「働き方開拓」についてもお聞きします。SSTは「時短勤務制度」も非常に充実していますよね。
江澤 私が人材開発部の部長に着任する前から、SSTには時短勤務制度があり、お母さん社員はすでにその制度を利用して働いていました。でも、その人たちがなんとなく肩身の狭い思いをしていると感じていて。なぜ、育児も仕事も頑張っている人たちが肩身の狭い思いをしなければいけないのだろうと思っていたんです。「私はフルで働けないから申し訳ない」とか、二言目にはそんな言葉が出てきてしまっていて、そう思わせてしまう環境を変えたいなと。なので、“時短勤務制度Ver.2”として、申請をして受理されれば誰もが時短で働けるようにとルールの改定をしました。つまり、この制度を使えるのは育児をしている社員だけではなくて、他にも親の介護とか、もちろん自身の体調のためとか、あるいは自己研鑽のための時間が欲しいとか、全従業員が取得できるもの、ということにしたんです。それによって変な意味での特別感や不平等感が払拭されて、誰もが堂々と時短勤務ができるようになりました。
つまり、SSTの時短勤務制度は、よく言われている「女性活躍」という目線での制度ではないんですよね。一貫して、全社員が、長く活躍できる会社にしていきたいという思いから「働き方開拓」に取り組んでいます。その中で、どうしても女性は出産や育児によって身体的にも休暇が必要な場面や、サポートが必要な人が多いということで、制度はまず女性の働きやすさに基準を合わせておく。けれど、その制度は誰が利用しても良いので、その結果として男性社員にとっても働きやすい環境になっているのだと思います。

──コロナ禍における外出自粛により、実店舗の営業に影響が及んだことと思います。今、店舗の営業、もしくは現場で働くスタッフとのルールや制度、思いの共有などにおいて、特に大事にしていることをお聞かせください。
江澤 社内でもオンラインでのコミュニケーションが主流になってきています。距離が離れていてもすぐにみんなが集まれる便利さもありながら、一方で、直接会って話すからこそ伝わることやできることがあることも実感しています。「お互いに温度感を伝えながら進めていかないといけない」と感じたときは直接会ってコミュニケーションを取る、その機会を持つことが必要だと思っています。
実店舗においては、新型コロナウィルスの影響でお客様が減ってしまっている状況ではありますが、今までの状態から変わることを恐れずにいたいです。 今、店舗に来てくださるお客様や働いているスタッフが求めていることは何か、ということを常に考えながら、世の中の流れに応じてゆく。「以前はこうだった」ということにこだわるのではなく、自分たち自身をどう変革するか──変えるべき部分と変わらない部分を取捨選択しながら、“今”できることに目を向けることが重要ですね。
TEXT:杉浦美恵、画像提供:株式会社スープストックトーキョー
※日本IBM社外からの寄稿や発言内容は、必ずしも同社の見解を表明しているわけではありません。
女性技術者がしなやかに活躍できる社会を目指して 〜IBMフェロー浅川智恵子さんインタビュー
ジェンダー・インクルージョン施策と日本の現状 2022年(令和4年)4⽉から改正⼥性活躍推進法が全⾯施⾏され、一般事業主⾏動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主 […]
Qiskit Runtimeで動的回路を最大限に活用する
私たちは、有用な量子コンピューティングのための重要なマイルストーンを達成しました: IBM Quantum System One上で動的回路を実行できるようになったのです。 動的回路は、近い将来、量子優位性を実現するため […]
Qiskit Runtimeの新機能を解説 — お客様は実際にどのように使用しているか
量子コンピューターが価値を提供するとはどういうことでしょうか? 私たちは、価値を3つの要素から成る方程式であると考えます。つまりシステムは、「パフォーマンス」、「機能」を備えていること、「摩擦が無く」ビジネス・ワークフロ […]