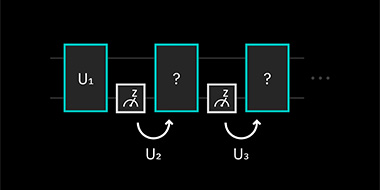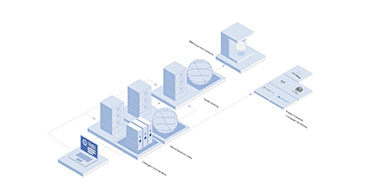Mugendai(無限大)
障がいがあるからこそ描ける世界――ビジネス目線で、福祉の可能性をプロデュース!
2020年9月3日
カテゴリー Mugendai(無限大)
記事をシェアする:
「異彩を、放て」というミッションを掲げ、福祉を起点に新たな文化をつくりだすことを目指す株式会社ヘラルボニー。代表取締役社長の松田崇弥氏と代表取締役副社長の松田文登氏は一卵性双生児であり、4歳年上の自閉症の兄への偏見に感じた違和感を原体験として、同社を起ち上げた。
知的障がいのある人々を取り巻く偏見や環境を改善させるため、彼らが生み出す、鮮やかな色彩や緻密な反復作業から生み出されるアート作品に着目。それらを、ネクタイなどのプロダクトにしたり、建設現場の仮囲いに展示したりすることで、障がいのある人々の存在をより身近なものし、彼らへ正当な評価と賃金が行き渡る事業づくりに取り組んでいる。福祉、ビジネスを柔軟な発想で掛け合わせ、社会を変革しようとしている2人に話を伺った。

ビデオ通話にてインタビューを実施。(左・崇弥氏、右・文登氏)

(まつだ・たかや)
株式会社ヘラルボニー代表取締役社長
チーフ・エグゼクティブ・オフィサー。小山薫堂率いる企画会社オレンジ・アンド・パートナーズ、プランナーを経て独立。異彩を、放て。をミッションに掲げる福祉実験ユニットを通じて、福祉領域のアップデートに挑む。ヘラルボニーのクリエイティブを統括。東京都在住。双子の弟。日本を変える30歳未満の30人「Forbes 30 UNDER 30 JAPAN」受賞。

(まつだ・ふみと)
株式会社ヘラルボニー代表取締役副社長
チーフ・オペレーティング・オフィサー。大手ゼネコン会社で被災地の再建に従事、その後、双子の松田崇弥と共にヘラルボニー設立。自社事業の実行計画及び営業を統括するヘラルボニーのマネジメント担当。岩手在住。双子の兄。日本を変える30歳未満の30人「Forbes 30 UNDER 30 JAPAN」受賞。
障がいは個性や可能性である
――福祉を軸に事業を展開する背景には、お2人のお兄さまの存在が深く関わっていると伺っています。ヘラルボニー起業までの経緯をお聞かせください。
崇弥 幼少期から僕たち2人とも、障がいのある人に対してバイアスがかかっていることに強い違和感を覚えていました。「お前たちは兄貴の分まで一生懸命生きるんだぞ」と親戚から言われたり、プールに行くと同年代が兄を指差して笑っていたり。家族の中で兄は楽しそうに暮らしているにも関わらず、一歩社会に出ると「障がい者」という枠組みで「かわいそう」とか「変な人」になってしまうんです。その状況をなんとかしたいという思いを、ずっと抱えていました。
文登 起業の直接のきっかけとしては、岩手県花巻市にある「るんびにい美術館」での崇弥の体験ですね。アウトサイダー・アート(知的障がいや精神障がいのある人など、伝統的芸術訓練を受けていない人の作者が創造した表現作品)を見て、深く感動したと話してくれたんです。僕もそれらの作品を見たとき、自分では到底描き出すことができない世界に感銘を受けました。
そこで、崇弥は広告代理店に、僕はゼネコンに勤務しながら、仲間たちと「MUKU」というブランドを立ち上げて、作品をモチーフにしたネクタイや傘のプロデュースを始めました。すると想像以上の反響があり、起業に対するマインドが自然に芽生えていった感じです。より多くの方に見ていただくことで、僕たちが感じたリスペクトが連鎖し、障がいがある方に対するイメージが変容していけばと思いました。

「MUKU」のネクタイ
――ヘラルボニーのミッション「異彩を、放て」にある「異彩」は、障がいがある人々の個性や可能性を指しているそうですが、具体的にどのような個性や可能性を見出しているのか教えてください。
崇弥 たとえば、自閉症の方にはスケジュールや決まった行動にこだわるルーティンの特徴があります。僕たちの兄は、日曜日の18時に必ずテレビで『ちびまる子ちゃん』を見ていたのですが、毎週見ているテレビ番組が打ち切りになると取り乱してしまう方もいらっしゃるようです。こうした生活の繰り返されるルーティンが、キャンバスに場所を移すと、色を繰り返し重ねたり、ひたすら葉っぱのような同じモチーフを描き続けたりと、独特な作品を生み出すことに繋がるんです。
それらの作品を目の当たりにすると、彼らだからこそ描ける世界があり、できる仕事があることがはっきりとわかります。障がいのない人は持っていない能力を「異彩」と表現することで、「障がい者」というくくり方ではない彼らの可能性にスポットライトを当てたいと思いました。
――今まで「異彩」が着目され、ビジネスにならなかったのはなぜでしょうか?
文登 福祉施設職員の方は障がいのある方の就労支援をするという立ち位置で、大抵はビジネスを専門的に学ばれているわけではないので、今既にある強みを伸ばして、どうお金を生み出していくのかというビジネス的発想にならないのは仕方ないことだと思います。たとえば、障がいのある方が5日間かけてつくった革細工がわずか500円で販売されるのが現状です。そこには「支援」の意味を込めてお金を払う仕組み以上の概念はないんです。支援ではなく、アート作品への対価としてお金を払う仕組みをつくるのは福祉領域だけでは難しいので、僕たちのようにビジネスとの接着剤的な立ち位置を担う存在が必要だと思っています。
40人のうち3人が熱烈に評価してくれるものをつくる
――2018年7月にスタートしたヘラルボニーは、事業拡大をしながら3期目を迎えました。日本ではアートをビジネスとして成功させるのは難しいとされる中、どのような経営戦略をお持ちでしょうか?
文登 弊社は「アパレル」のほかに、「原画の複製」「ライセンス」という3本柱で事業を展開しています。原画の複製は、アートに特化した福祉施設と契約を結び、複製画を販売することで原画の価値を向上させることを目的としています。ライセンスに関しては、約2,000作品のデータを所有しており、企業とのコラボ商品開発等、収益面でも成長が見込める分野です。アート作品の使用料として商品販売価格の一部が弊社にバックされ、障がいがある作家さんに継続的に賃金をお支払いできる仕組みを想定しています。崇弥が前職でキャラクタービジネスをやっていたので、そのノウハウが生かされている分野ですね。
崇弥 ターゲットの話をしますと、福祉やアートは、「私には関係ない」と遠ざけられがちです。なので、会社を設立した際に、僕たちの地元、岩手県の友だちを顧客として想定しました。彼らは福祉やアートには興味がなくても、supremeやコム・デ・ギャルソン、イッセイミヤケは購入します。そこから、アートやブランドが、モノに落としこまれたときに、より多くの人に伝わる可能性が生まれるのではないかと考えたのです。

吉本興業とのコラボブランド「DARE?(ダレ?)」
崇弥 文登とよく話しているのですが、40人いたら半数の20人に刺さるようなことはあまりしたくないと思っています。40人の内たった3人が熱烈に評価してくれるプロジェクトを複数走らせたいんです。たとえば、弊社のアパレルブランドは、クリエイティブを尖った印象にしていますし、吉本興業さんと一緒につくったブランド「DARE?(ダレ?)」ではお笑いと一緒にアートで変えていくことをコンセプトにしていて、それぞれ違う層に刺さるようにしています。
文登 いろいろなカテゴリーで熱烈なファンをつくり、その輪が広がって、最終的に障がいへのイメージを変容するという自分たちの目的を達成できればという思いです。
三方よしのビジネスモデルだからこそ展開できる
――ライセンス事業の一環として、建設現場の仮囲いにアートを掲載する「全日本仮囲いアートミュージアム」を展開されています。これはゼネコンで働いていた文登さんのアイデアでしょうか。
崇弥 そうですね。「仮囲いにアートを貼ったら絶対にいける!」と文登が言い出したときは驚きました。仮囲いに何も貼らず真っ白なままにしているゼネコンが多いことから、そこにアート作品を貼り、作家に使用料が還元されるモデルプランを説明されたのですが、当初は成功するのか半信半疑でした。それが今や全国10箇所以上で仮囲いアートミュージアムが進行しているほどの事業になっています。
文登 ゼネコンに勤務していたので「工事成績評定」という工事の成績表のようなものがあることは知っていました。公共工事が完成した段階で発注者が施工状況や出来ばえ、技術提案などを採点し、80点以上だと次の入札公示で優遇されやすいと言われています。そこで、仮囲いのアートミュージアムを「工事成績評定」の加点プログラムにできないか、地元の岩手県議会議員にかけあって、加点対象と認定してもらったのです。
――企業にとっての利益にもなる仕組みをつくったのですね。
文登 「障がいがある人のアートを展示しましょう」と呼びかけるだけでは、実現させることは難しいので、ゼネコンにとってわかりやすいベネフィットをどう提示できるか考え抜きました。たとえば、知名度を上げたいゼネコンは、普通なら新聞広告などを掲載しますが、「同じ金額で仮囲いにアートを掲示すれば、SDGsやCSVといった視点を備えたプロジェクトとしてもアピールできますよ」と戦略的に働きかけることで、採択に結びつけています。
――高輪ゲートウェイ駅にて実施された「Takanawa Gateway Fest」での仮囲いミュージアムでは、アート作品をトートバックにアップサイクルして、事業者にも還元するという新モデルも構築されています。
文登 光栄なことにJR 東日本スタートアップ株式会社のプログラムに採択していただき、耐久性の高いターポリン素材にプリントしたアート作品を展示した後に、それをアップサイクルし、トートバックとして販売する予定です。仮囲いを彩ったターポリンが再利用されるとともに、商品販売によって得られた利益の一部をアーティストや事業者に還元できるプロジェクトになっていることが特徴です。

崇弥 街中にミュージアムがあるだけではなく、トートバックやペンケースなどアップサイクルするグッズを増やすことで、仮囲いが販売チャネルにもなるのです。また、商社や大企業のほうが作品をより効率的に広める力を持っているので、弊社は将来的に他企業と契約を結ぶライセンサーの立ち位置になれたらと思います。そうなるために、自分たちでも仮囲いプロジェクトの可能性を見せていく必要があるので、現在、担当スタッフを増員し注力しているところです。
――お兄さまの存在や、福祉施設と信頼関係があることが御社の強みになっていると感じます。信頼関係を構築できた理由はどこにあるとお考えでしょうか?
文登 福祉の分野でビジネスの話をすると、「そこまではちょっと」という雰囲気になってしまうことがしばしばあります。なので、「障がいがある方の個性が評価される仕組みをアートを通じて構築したい」という弊社の思いをしっかりとお伝えするようにしています。
崇弥 根底にあるのは、できないことを補おうとするのではなく、できることに照準を合わせた仕事づくりが実現できれば、さまざまな能力を生かせる社会になるはずだという思いです。なので、アーティストには、プロジェクトの納期は伝えますが、けっして無理強いはしません。納期に間に合わなければ、僕たちがクライアントに頭を下げる覚悟で、余裕を持ったスケジュールやスピードを補完するように努めています。
そうして製作したネクタイを持っていったとき、福祉施設の方は「ここまでクオリティの高いものになるとは思っていませんでした」と感激されていました。施設だけでは完結できないレベルのモノづくりに到達できていることや、ひとつひとつ一緒に積み上げてきたことを評価していただいて、信頼関係に繋がっているのだと思います。
福祉、支援を超えるビジネスの可能性を追求
――2020年2月に「この国のいちばんの障害は『障害者』という言葉だ」という意見広告を出されています。その背景には、言葉からマイナスイメージを連想してしまう社会への問いかけがあったのでしょうか。
崇弥 実は、「知的障がい」という言葉は、古くは「白痴」から「精神薄弱」に、そして「知的障がい」に……と、まだマイルドな表現に変わってきてはいますが、それでも言葉から想起されるイメージが今の時代にふさわしいか疑問です。自治体に障がい者と認定されることで支援を受けることができますし、枠でくくることが悪いことだとは思いません。ただ、くくり方を見直すべきではと考えています。

「#障害者という言葉」の意見広告
――先ほどの、一歩社会に出ると「障がい者」という枠組みで「かわいそう」と捉えられてしまうというお話にも繋がりますね。今後のご予定として、地元の岩手県では、百貨店に実店舗出店、オフィス兼ギャラリーのオープン、さらには内装やコンセプトを手掛けるホテルが完成するなど、盛り上がりを見せていますね。
文登 事業を始めてから2年、本当にいろいろな方に支えていただきました。僕たち2人だけのアイデアというわけではなく、多くの方と一緒にひねり出したというか、こうやったら社会が変わるんじゃないかと考え続けてきた結果です。
ジェトロ(日本貿易振興機構)の支援を受けることが決まり、アウトサイダー・アートのマーケットがあるイギリス、米国、中国でもチャレンジする予定です。日本の障がいがある方のアートが、世界でどのように評価されるのかすごく興味があります。
崇弥 多くの組織や企業の方々と手を組ませていただいていますが、社会貢献が先立っているのではなく、きちんとアウトサイダー・アートにビジネスチャンスを感じてくださっている方かどうかは重要視しています。企業の中でSDGsへの配慮が重要視されてきていることは理解していますが、その文脈を打破できなければ本当の成長はないと考えているからです。

るんびにい美術館のアーティストと
――数多くのプロジェクトが進行し、これからは「選択と集中」や意思決定が大事になっていきそうですね。
文登 自分たちが良いと思うことをひたすらにやってきたので、そろそろ戦略的に選択していく必要があります。崇弥が社長としてクリエイティブを、僕が副社長でマネージメントを担当し、全て相談していますが、些細なことで対立もします(笑)。他のスタッフには優しくできることでも、崇弥には正直になりすぎて、はっきり言ってしまうんです。
崇弥 文登は本社がある岩手を、私は東京を担当しているので、一緒にいないのが良かったと思う時もあります。電話で喧嘩になっても、どちらかが一方的に切るので(笑)。もちろん、普段は仲良く、頻繁に相談しあっていますよ。
文登 経営者のメンタルヘルスケアは大変だという話を聞くことがありますが、僕は崇弥と一緒に決断することができますし、同じ思いを共有できているのでありがたいです。
僕たちがやっていることに続いてくれる企業がいれば嬉しいですし、ヘラルボニーが目指してもらえるような対象になれたら、社会は確実に良い方向に変わっていくと信じています。
TEXT:小林純子、写真提供:株式会社ヘラルボニー
※日本IBM社外からの寄稿や発言内容は、必ずしも同社の見解を表明しているわけではありません。
関連リンク
女性技術者がしなやかに活躍できる社会を目指して 〜IBMフェロー浅川智恵子さんインタビュー
ジェンダー・インクルージョン施策と日本の現状 2022年(令和4年)4⽉から改正⼥性活躍推進法が全⾯施⾏され、一般事業主⾏動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主 […]
Qiskit Runtimeで動的回路を最大限に活用する
私たちは、有用な量子コンピューティングのための重要なマイルストーンを達成しました: IBM Quantum System One上で動的回路を実行できるようになったのです。 動的回路は、近い将来、量子優位性を実現するため […]
Qiskit Runtimeの新機能を解説 — お客様は実際にどのように使用しているか
量子コンピューターが価値を提供するとはどういうことでしょうか? 私たちは、価値を3つの要素から成る方程式であると考えます。つまりシステムは、「パフォーマンス」、「機能」を備えていること、「摩擦が無く」ビジネス・ワークフロ […]