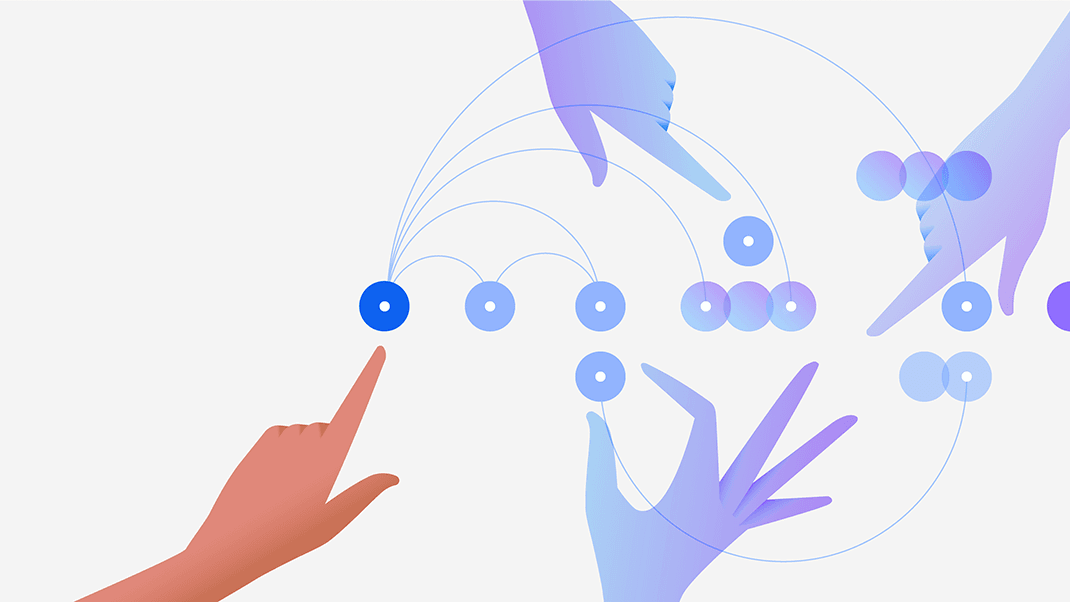※新型コロナウイルスの拡大防止に最大限配慮し、写真撮影時のみマスクを外しています。

玉那覇 寿彦 氏
株式会社琉球銀行
事務統括部 事務企画課 調査役
入行後、営業店 2カ店にて窓口・個人営業・融資業務を経験した後、営業統括部営業企画課で CRM や通帳アプリを担当。2022 年 4 月より、事務統括部事務企画課にて店頭タブレットシステム(FTB)に携わり、機能改善や運用に従事している。

渡邉 学
日本アイ・ビー・エム株式会社
IBMコンサルティング事業本部
金融ビジネス・ソリューションズ 営業推進
2002年日本IBM入社、コンビニATMやインターネットバンキング関連ソリューションの担当を経て、現在は店舗や金融機関事務のDX推進ソリューションを含め幅広く金融機関チャネルソリューションを担当している。
ネット銀行や小売系銀行の進出により金融機関の競争が激化する中、地方銀行では営業店をいかに活用するかが一つの課題となっています。株式会社琉球銀行(以下、琉球銀行)は有人店舗チャネルを地方銀行が持つ最強の地域ネットワークとして重視し、その価値を高めるべく営業店変革に取り組みました。銀行サービスの差別化の源となる「人材」を、事務作業から本来求められている金融サービスの提供へシフトするため、営業店に「FTBタブレットシステム」を導入。顧客の利便性を高めると同時に、ペーパーレス、印鑑レスなどにより事務処理時間を大幅に削減するなど、効果を上げています。変革の狙いやプロジェクトの実際について、システム運用を担当する同行事務統括部事務企画課の玉那覇寿彦氏と、構築推進をサポートしたIBMの渡邉学に話を聞きました。
店舗チャネルは人的サービスを提供できる唯一無二の存在

琉球銀行は、「地域から親しまれ、信頼され、地域社会の発展に寄与する銀行」を経営理念に掲げ、地域のニーズに応えています。近年、来店者数の減少や競合企業による競争が激化する中、同行では差別化を図るべきところは「人」の魅力と価値であり、店舗チャネルは人的サービスを提供できる唯一無二の存在と考えています。
一方、営業店での窓口対応に目を向けると、行員は紙をベースとする事務処理に多くの時間を割き、金融サービスではなく、事務サービスを提供する場になっているのが現実でした。
「銀行の事務は複雑かつ厳格化されているところがあります。お客様に対してもその事務ルールを強要してしまうことで顧客満足度を下げるとともに、処理の迅速さや正確性を求めすぎた結果、従業員満足の低下も招いてしまっていました」と玉那覇氏は説明します。
また、営業店における事務処理件数は全チャネルの15%程度でありながら、約63%のコストがかかっており、高コスト構造にあることがわかっていました。
このため琉球銀行では、営業店の存在意義向上と現状とのギャップを埋めるため、2018年6月、「次世代営業店構築プロジェクト(通称FTBプロジェクト)」を立ち上げました。
「FTB」とは、「Flexible & Traditional Bank(伝統と柔軟性を兼ね備えた銀行)」の略称です。「F」にはお客様に楽しんでいただける銀行であるFUN、行員自身も楽しく働けることのFUNと、琉球銀行のファンをつくるというFANという3つの想いが込められています。
なくせる作業はなくし、時代に合わせた対応を可能に
琉球銀行がプロジェクトの目標に掲げたのは、銀行最大の財産である「人材」を、事務サービスから本来求められる金融サービスの提供に振り向け、店舗価値と存在意義の再構築を図ることです。実現を支えるシステム・インテグレーターにはIBMを選定しました。玉那覇氏は「なくせる事務作業はなくす、誰でもできる事務処理にする、そして時代に合わせた対応をする、という3つの観点から想いに応えていただけるパートナーがIBMでした」と振り返ります。
システムは、店頭で使うタブレットシステムとホストを直接つなげるとなると、大規模な改修となることが予想されました。そのため、2つのシステムを営業店端末のアプリケーション「TfACE」経由で接続し、端末のオペレーションをせずともタブレットのボタン操作を通じて事務処理をワンストップで完結できるようにしました。
また、将来の拡張性を見据え、他の基盤との接続を可能にするAPI接続基盤を整備。コストを抑えつつ、時代に合ったソリューションを導入可能にしています。
FTBシステムでは、営業店舗でこれまで紙で記入していた手続きに必要な情報を、タブレットでの処理に移行するため、「受付用」「行員用」の2種類のタブレットを導入しました。受付タブレットは、従前の発券機の役割も果たすとともに、付属機器としてキャッシュカードや通帳を用いて本人情報を取得するための磁気リーダーが付属されています。一方、行員タブレットには、受付タブレットで取得した顧客情報が連携されており、即座に顧客情報を呼び出し、後続処理ができるようになっています。
事務の省力化にあたっては、印鑑レスも進めました。印鑑の代わりにキャッシュカードや通帳で本人確認する点について、当初は現場で不安の声もあったといいます。「リーガル部門であるリスク統括部とも連携し、暗証での認証によりリスクが上がるものではないと判断しました」(玉那覇氏)
綿密に計画、準備した上で、22業務を一気に変更
プロジェクトの対象となる業務について、琉球銀行はまず個人向け業務の80パーセントに当たる30業務を抽出しました。事務統括部のメンバーが営業店を回り、各業務のオペレーションにかかる時間を実際にストップウォッチで計測して、状況を把握。普通・定期の口座にかかる開設や解約、変更など、処理にかかる時間や手間が多い22業務に焦点をあてるよう計画しました。
従来、帳票と印鑑で対応していた業務を、タブレットですべて行えるようにしたことについて玉那覇氏は、「大きな変革でしたので、もちろん営業店は大変だったと思います。研修を重ね、行内向けに利用イメージをもってもらうための動画もつくりました」と話します。導入当初、当時のプロジェクトマネージャーをはじめ事務統括部、事務手続きの流れを知っている担当者、臨店担当者、研修担当者ら10人がチームとなって、各営業店に臨店してサポートを続けたといいます。
そして琉球銀行は最初に22業務を一度に導入します。このことについて玉那覇氏は、「銀行として取り組みが本気であることを示すためにも、現場の方に意識を切り替えていただくためにも、インパクトが必要でした」と明かします。
一方、IBMの渡邉も「結果が明らかに予測できるものについては、最初から一気に進めるほうがいい場合があります。今回のプロジェクトは、導入効果を事前に計算できていました」と自信を見せます。
目に見えたFTBタブレットシステムの導入効果
新システムの店舗への導入は、2019年10月にまず2カ店で試行を始め、2021年8月に全店展開を完了させるという、約3年というスケジュールで進められました。全店展開後も「レベルアッププロジェクト」として、機能の改善・追加を2022年12月までの予定で行っています。
タブレットによる処理率は、相談窓口業務の70パーセントを超え(2022年10月時点)、事務処理時間の削減率も、当初の目標だった50%を超え、62%を実現しています。これは時間に換算すると、年間で約60,000時間の削減に相当します。またペーパーレス化により、年間で約126万枚の帳票削減効果も上がっています。
玉那覇氏は「ペーパーレスによる業務効率化はSDGsにも直結し、ひいては企業価値の向上に寄与します。さらに行員からは『直感的に操作でき、事務処理に迷うことなく、ストレスも緩和された』という声もあり、従業員満足度向上にもつながっています」と説明します。
また、店舗を利用するお客様にとっても、「従前より手続きが楽」「早い」「便利」「紙への記入の負担が減った」という高い評価が約9割を占めました。
タブレット操作については、現在、多くの金融機関などが導入しています。完全にお客様が行う「セルフ」と、行員がサポートする「セミセルフ」がありますが、琉球銀行は後者で、お客様だけで完結させる業務はないといいます。
「完全セルフでできる取引はバンキングアプリに誘導しています。せっかく来店して、対面しているのですから、コミュニケーションの時間を大事にしたい」と玉那覇氏は強調します。
仲間(SINKA)とともに進化し続ける

今回のプロジェクトで、現在30種類の取引業務において事務処理のデジタル化が実現しました。今後はさらに対象業務を拡充するとともに、利用シーンの拡大も見込んでいます。
「行員側にお客様情報が通知された際に、提案すべきサービスがポップアップ表示されれば、経験の浅い行員もお客様のライフステージに応じた資産運用の提案などができるようになります」(玉那覇氏)
琉球銀行は、お客様一人ひとりのニーズに合った提案をすることで、さらなる顧客満足向上につなげる計画です。
事務処理の30業務、6割削減という大きな成果について、渡邉氏は「銀行側が主体的に自分たちの意志で変わろうと思っていたからこそ、どうすれば最大限に効果を出せるか、成功できるかを追求していくことができました」と語ります。
システム開発にはシステムベンダーの協力は必須ですが、銀行業務の課題や改善ポイント一番理解しているのは銀行です。当事者が主体的にかかわり、銀行側の目線でプロジェクトを進めたことが、より使いやすいシステムの構築につながり、大きな成果を生みました。渡邉氏は、「銀行によって考え方は異なりますが」と前置きをした上で、「地銀には地銀にしかない地場に根付いたリアルのチャネルがあります。そのチャネルを活かすために何を加えるべきか、何を削減すべきか。今後もDX化で差別化を図る手伝いをしていきたい」と話します。
玉那覇氏も「IBMはFTBタブレットシステムを構築から運用まで二人三脚で作り上げてきたパートナーであり仲間です。これからも仲間(SINKA)とともに進化(SINKA)していきたいです」と熱く語ります。
地銀の強みを生かしつつ、地域に貢献していくために琉球銀行はこれからも歩み続けます。
関連リンク
デジタル・テクノロジーによる金融ビジネス変革の実現についてはこちらをご覧ください。