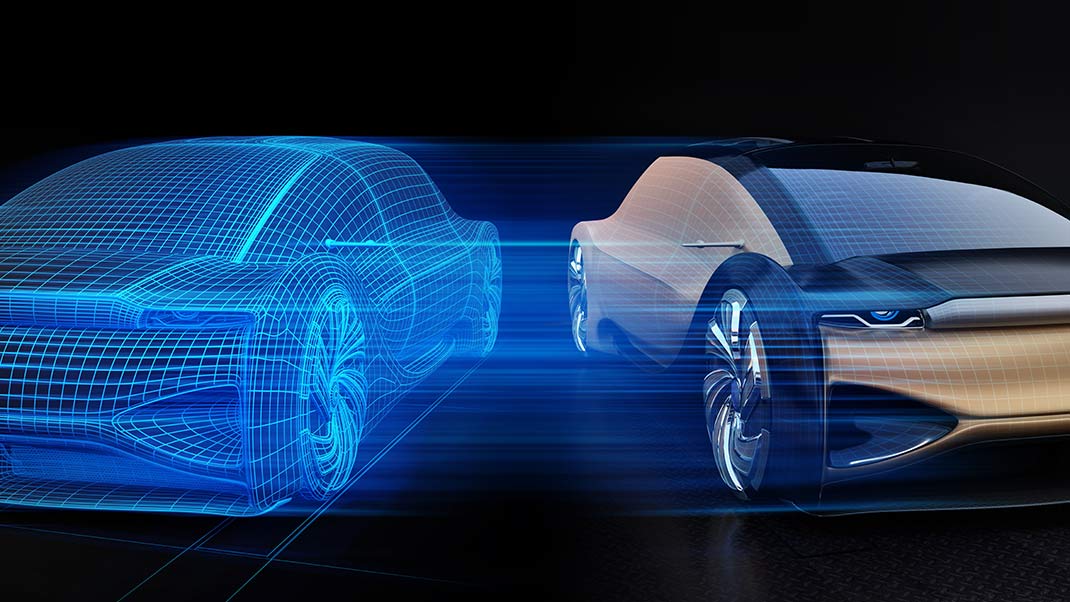川島 善之
日本アイ・ビー・エム株式会社
IBMコンサルティング事業本部
グローバル オートモーティブ
コンピテンシー センター アジア地区リーダー
日本IBM 自動車産業担当 CTO
長年にわたり日本IBMで日系自動車OEMを国内外から支援し、OEMの現場経験を豊富に持つ。特に海外現場での現地メンバーの統率を得意とする。2014年より 「つながるクルマ」や「要求仕様設計」に携わり、最近はクルマの要素技術に限らず、半導体やエネルギー関連の部署とも連携して活動中。

若林 秀彦氏
Red Hat, Inc.
In-Vehicle OS, Product & Technology
Principal Eco System Development Manager, In-Vehicle OS
車載ソフトウェアのためのオートモーティブエコシステムの開発、自動車メーカー向けSoftware Defined Vehicle Architectureのコンサルティング支援を行っている。APAC、日本、韓国及び中国を担当。

井上 陽治氏
レッドハット株式会社
エンタープライズ事業本部
製造・サービス事業部 ソリューションスペシャリスト
製品開発、プロジェクトマネージメント、プリセールス等の経験を経て、現在はお客様のデジタルトランスフォーメーション実現のためにオープン・ハイブリッドクラウド、AI/MLプラットフォーム等の提案を行っている。
自動車づくりの世界が大きく変わろうとしている。自動車に多くの電子部品が搭載され、ソフトウェアがそれらをコントロールする電動化がますます加速し、ソフトウェアが自動車を定義する、Software Difined Vehicle(以下、SDV)の時代が訪れることが予想されている。そこで求められているのが、ハードウェアとソフトウェアの進化の速度の違いを吸収できる車載OS・ミドルウェアであるVehicle OSだ。自動車の未来の姿を支えるVehicle OSにはどのような要件が必要であり、どんな技術やソリューションが重要になってくるのか――。IBMとRed Hatの3名のスペシャリストに話を聞いた。
メカトロニクスとソフトウェアで
新たな顧客体験を生み出していく
――現在のクルマの姿をどのようにとらえていますか。
川島 昨今、乗用車の長期使用化が進むとともに、クルマの姿は大きく変わりつつあります。クルマが純粋に機械式の製品だった頃に誕生し、長く生産されていた欧州車がありましたが、そのクルマは30年先まで見越して多様な機能が盛り込まれていました。一方、現在求められているのはソフトウェアが定義するクルマ、SDVです。クルマがハードウェア製品にとどまらず、ソフトウェアによって進化する。すなわち、クルマの機能は「クルマ」というプラットフォームを利用したユーザー視点でのサービスになり、メカトロニクスとソフトウェアによって生み出されるようになりました。さらにクラウド基盤とつながることでクルマのデータが外部に送られ、利用しやすい形に加工されて戻ってきたり、分析されて新製品の設計にフィードバックされるようになってきています。
――そのような時代にあってOEMには何が求められるでしょうか。
川島 クルマがクラウドとつながってリモート・コントロールできるようになると、OEMはセキュリティーも含めて考えていかなければなりません。一方、SDV自体に決まった定義はありません。基本的な機能や拡張サービス、セキュリティー、提供されるコンテンツを含めて、ユーザー視点で何を提供できるかを考えていく必要があります。
――IBMはOEMをどのようにサポートしていきますか。
川島 IBMは大きく3つのビジネスゴールを掲げています。1つ目は「車両品質の向上」です。エンジニアリング・ライフサイクル・マネジメントというツールを使い、テンプレートを各種提供して、ASPICEフレームワークに準拠して機能安全を確保した車両開発のプロセスをサポートします。2つ目は「再利用性の向上」です。エンジニアリング・ライフサイクル・マネジメントのツールを通じて、E/E(電気/電子)アーキテクチャーとソフトウェアの再利用を単一のプラットフォームで可能にしていきます。3つ目は「オンタイム開発」。開発プロセスにアジャイル開発の要素も加えて、システム、ソフトウェア、E/Eエンジニアリングをサポートします。
――3つの目標を実現していくためにはどのような技術がカギになってくるでしょうか。
川島 今後重要になると考えているのが、Linuxの適用であり、コンテナ技術の適用です。これまで専用OSを開発したり、オープンソースを活用して専用OSを開発してきましたが、今注目されているVelicle OSは単一のOSで成り立つものではなく、フレキシブルに機能更新するためにコンテナ技術が重要になります。こうした流れを受けて、Red HatはSDVを支える新世代の車載OS「Red Hat In-Vehicle Operating System」の開発に取り組んでいます。
統合化ユニットに複数のアプリを搭載し
クラウドとの連携で継続的な進化を
――Red HatはSDVへの動きをどのように見ていますか。
若林 これまでクルマはコネクテッド・カーに向けて進化してきました。現在の車載ECU(Electronic Control Unit)のアーキテクチャーは特定の機能を提供するものであり、Red HatではそれをVehicle 1.0と定義しています。次にデジタル化された段階がVehicle 2.0、さらにアップデートが可能になるのがVehicle 3.0。そして、クルマとさまざまなサービスがオンデマンドでつながる「Mobility as a Service」が実現されるVelicle 4.0へと段階的に進化していくと見ています。
――進化に伴い、車載OS、ECUのアーキテクチャーの構成も変わりますか。
若林 ハードウェア中心の世界からソフトウェアで定義し、クラウドとつながる世界へとシフトする中で、ECUの構成も変化していきます。従来は個別のECUが特定の機能を担ってきましたが、クルマの中心には“ゾーンECU”とも言われるHPC(High Performance Computing) Platformが配置されるようになります。HPC Platformの中にはコンテナ技術を活用して複数の機能が搭載され、ECUの数自体はこれまでより少なくなります。統合化されたHPC Platformに搭載されたアプリケーションによって、クルマの各機能がコントロールされるようになるのです。
――現在開発中の車載OSである、Red Hat In-Vehicle Operating Systemについて簡単にご紹介ください。
若林 現在Red Hatでは、CentOSをベースに車載OSに必要な要件を議論し、開発を進めています。「Open」「Safe」「Secure」の3つをコンセプトに掲げ、オープンソースのコミュニティーであるCentOS Stream Automotive SIG、ELISA、ISO 26262 evolutionと連動しているのも大きな特徴です。機能安全はOS単体でASIL-Bをサポートしており、それはソフトウェアのアップデート等のイベントにおいても継続的にサポートされます。オープンソースで透明性が高い点、さらにLinuxベースのためアプリ開発の柔軟性が⾼い点もアドバンテージになると考えます。
――どのようなユースケースが想定されますか。
若林 統合コックピット、IVI、ADAS、セントラルECUのGateway機能などをユースケースとして想定しています。特にミクスト・クリティカリティーが要求されるECUは最適だと考えます。
――車載OS以外にRed HatがSDVの中でフォーカスしている領域はありますか。
若林 SDVで必要となるのはクルマの車載OSだけではありません。クルマとクラウドをつなぐConnected Velicle Platformやクラウド側からクルマにサービスを提供するDevelopment and Testing、製造工程でもクラウドを活用するManufacturing ITなどのソリューションも必要になります。Red Hatでは、このVehicle Offboardと呼ばれるプラットフォームにも製品やサービスを提供していきたいと考えています。
エッジコンピューターに向くコンテナが
SDVの世界を大きく変えていく
――井上さんにはRed Hatの車載OSで使われているコンテナ技術について伺います。コンテナを使うメリットはどのようなところにありますか。
井上 コンテナのメリットは多々ありますが、まず「可搬性」が挙げられます。可搬性は自動車を含めたエッジ・コンピューティングでは非常に重要な要素です。ある車種だと動いても別の車種では動かないという状況では開発効率が悪く、再利用性が低下します。一方、可搬性があれば個別のチューニングが必要なく、自動化やゼロタッチオペレーションも可能になります。
また「軽量」であり、「起動が高速」であることも大きなポイントです。エッジコンピューティングでは利用できるリソースが限られるので、軽量性は重要です。また、起動が速ければ、ダウンタイムを最小化することができます。コンテナは仮想マシンに比べて一桁以上軽量で、起動時間を数分から数秒に短縮できます。
――稼働環境についても教えてください。
井上 車載OSとしては一つのLinux上で複数のコンテナを同時に稼働できることも大きなメリットです。クラウドとも相性が合います。さらに隔離性が高いことも重要です。例えば統合コックピットでもインフォテイメントとメーターが独立しているので、インフォテイメントがクラッシュしてもメーターには影響がありません。
――SDVにおけるコンテナの価値をどのようにお考えですか。
井上 SDVにおけるコンテナの価値は3つあります。クラウド化を促進させること、エッジ管理を効率化すること、そしてクラウドとの相互運用性を実現することです。この3つによってSDVの世界は大きく変わっていきます。現在Red Hatではエッジ向けに軽量化したKubernetesも開発中です。
こうしたRed Hatの取り組みへの注目は高まっています。今年5月にはゼネラルモーターズ(GM)社が2023年にリリース予定の車載プラットフォーム「Ultifi」にRed Hatの車載OSの採用を検討することを発表しました。他にも欧州系のOEMや一部の国内のOEMと概念実証(PoC)に向けた話し合いも進行中です。各方面から同社が開発する車載OSに熱い視線が注がれています。