※新型コロナウイルスの拡大防止に最大限配慮し、写真撮影時のみマスクを外しています。
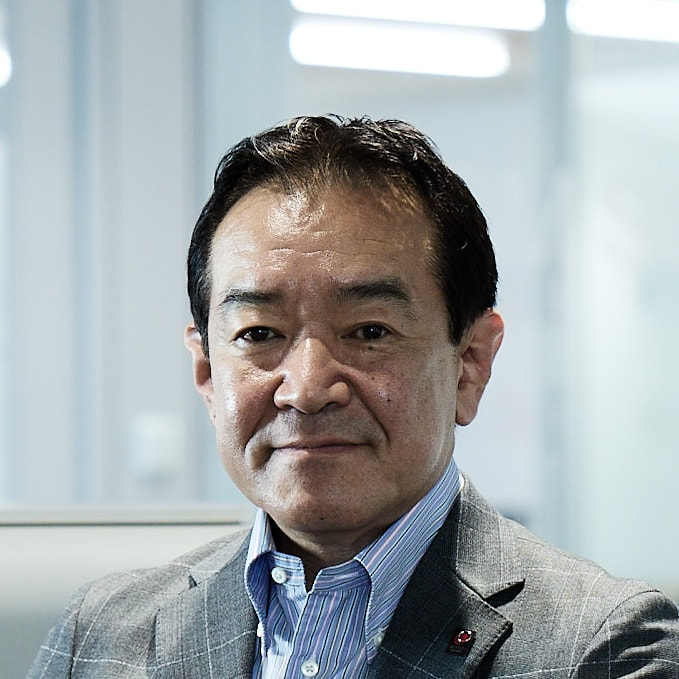
浦川 伸一氏
損害保険ジャパン株式会社
取締役専務執行役員CIO
SOMPOシステムズ株式会社
取締役会長
立教大学大学院 人工知能科学研究科
客員教授
立教大学社会学部卒業後、日本IBMを経て2013年に株式会社損害保険ジャパンおよび日本興亜損害保険株式会社執行役員CTO。2014年SOMPOシステムズ株式会社代表取締役社長、2016年損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員CIO。2020年損害保険ジャパン株式会社取締役専務執行役員CIO(現職)、2021年SOMPOシステムズ株式会社取締役会長(現職)。COBOLベースの現行基幹システムを日本初のJavaEE7をベースとしたオープンシステムに刷新するなど、斬新なデザインを提唱し実現に導く。社内外での講演や、内閣府、経産省、経団連などのDX推進、AI活用に関する委員会にて積極的に活動する。

藤田 通紀
日本アイ・ビー・エム株式会社
IBMコンサルティング事業本部
パートナー/保険インダストリー・リーダー 兼 保険ソート・リーダー
金融機関およびコンサルティング業界でのプロフェッショナルとして20年以上の経験を有し、経営戦略、セールス・マーケティング、教育・研修からオペレーション、またアートとデジタルなどの幅広い分野での専門性を有す。トランスフォーメーションに関わる実務と理論に基づいたアドバイザリー・サービスを提供。著作・講演多数。MSc(英ウォーリック大)、MBA(英ウェールズ大)、PgDip(英エクセター大)修了。
ソート・リーダーとして保険業界の経営戦略やデジタル改革を数多く共創してきた、IBMコンサルティング 保険インダストリー・リーダーの藤田通紀が聞き手となり、保険大手各社のデジタルシフトの担い手をゲストに迎え、保険業界の未来を探る対談連載。第4回は、損害保険ジャパン株式会社でITを統括する浦川伸一取締役専務執行役員とともに、保険業界におけるテクノロジーの役割について考えた。
損保ジャパンは2014年に旧損保ジャパンと旧日本興亜損害保険が合併して発足し、両社の基幹システムを統合。しかし、2つのシステムを一部併用する形ゆえに現場の負担が大きく、このままでは予測不能な「VUCA」の時代に対応できないという判断から、約34年ぶりの基幹系刷新に踏み切る。2021年3月、損保ジャパンのDXを後押しする新たな基幹システム「SOMPO-MIRAI」の第一期を本番稼働させた。
「SOMPO-MIRAI」ではシステム全体を小さなブロックに分割する「マイクロサービス」と呼ばれる構造が採用されているが、背景にはSOMPOホールディングスの桜田謙悟グループCEO会長が掲げる「Light Footprint(LFP、軽い足跡)経営」があったという。この対談では、保険業界のテクノロジー・トレンドから、テクノロジーを使いこなす人材や文化など、テクノロジーを軸に幅広く語り合った。
保険業界がテクノロジーとの共創によって向かう先

藤田 浦川さんは実務の世界でも学術の世界でも、AI活用・DX推進の専門家として著名な方です。立教大学大学院でもAIの社会実装をテーマに教鞭を執られていますが、読者に向けて簡単に自己紹介いただけますか。
浦川 1984年に日本IBM(以下、IBM)に入社してエンジニアを十数年、その後プロジェクトマネージャーを経て2013年までIBMにおりました。8年前にご縁があって転職、現在までIT部門を統括しています。
入社当時は旧損保ジャパンと旧日本興亜損害保険のシステム統合プロジェクトが進んでいましたが、すぐに次期システムを立ち上げたいということで、準備に取り掛かりました。その後CIOとして正式にプロジェクトを立ち上げ、アーキテクチャ・デザインを主導し、昨年無事に本稼働へと進むことができました。
藤田 ここ数年、保険業界のテクノロジー・トレンドは加速度的に進化している印象がありますが、産学両方の専門家である浦川さんはどのように見ていらっしゃいますか。
浦川 保険業界のテクノロジー活用が、10年後、20年後にどこまで進化しているのか、明確に予測できる人は世の中にいないと思っています。
IT業界に40年近く身を置いて実感していることですが、1960~70年代に培われた情報システムやソフトウェア・エンジニアリングの基礎はいまだ普遍性を保っているものの、それを取り巻く環境の変化は非常に激しいと考えています。
変化し続けているのは、人の生活様式や人生に対する価値観、あるいは物の価額※1の分野です。価額は時代とともに変わり、それに対して保険は掛けられるものですから、リスクもプライシング・メカニズムも当然変化していきます。
※1品物の値打ちに相当する評価額。 法律用語としては、具体的に特定した物、財産の金銭的価値を表すときに用いられる。
一方で、人の命のように普遍的な価値を持つものもあります。自動車も家も生きることに関わる大切な要素なので、そこに保険を掛ける。だとすれば、人や物が存在し続ける限り、世の中から保険が完全になくなることはないと思います。
藤田 保険という商品は、価額が変化する金融商品としての側面もあれば、生と死、事故や病気など、人という存在の変わらない価値に紐付く側面もある。変化するエリアと普遍的なエリア、その両面を持つのが保険ということですね。
その意味では、保険そのものの基本的な構造やバリュー・プロポジションが、テクノロジーの進化によって大きく変わることはない。しかし、テクノロジー、時代、ニーズによって変化する部分に対しては、保険の商品性やサービスを合わせていく必要があるということでしょうか。
浦川 バリュー・プロポジションは変わらないかもしれませんが、構造は大きく変わる可能性があると思います。例えば車を買うと、ディーラーやプロの保険代理店で自動車保険加入申込書をもらい、「この車にいくらの保険を掛けるか」を決めて契約しますね。
欧米ではすでに、OEM保険のような形で、自動車契約の中に保険が仕込まれているものがあります。また、「保険は運転する日だけスマホで入れば良い」というニーズを想定し、損保ジャパンがLINEと共同開発した「LINE ほけん」(現在はPayPayほけん)では、2018年から少額で入れる「半日からの自動車保険」というサービスを提供しました。自動車保険も、オンデマンドでスマホから契約を入れた瞬間にスタートする。そういう構造変化はすでに始まっていますね。
藤田 確かにテクノロジーを活用して運転の履歴を残せば、責任開始日も明確にできますね。こうしたアイデアは今後もたくさん出てきそうです。
浦川 これまでは車というIoTと保険を結びつけることが難しかったので、保険の始期と終期を定めて、1年間でいくらという契約にしていたわけです。しかし1年間、365日ずっと運転し続ける人はほとんどいらっしゃらないので、“オンデマンド”というのは、保険の今後における姿の一つだとは思います。
一方で、オンデマンドが保険の主力になるかどうかは、非常に興味のあるポイントです。そこに収斂していくと、保険マーケットは保険料収入が激減するなど極端にシュリンクしていきます。今後は移動や生活に関わること全般において、これまで想定もしていなかったリスクを想定した保険に分野が広がっていくのではないかと考えてみることも必要でしょうね。
藤田 保険業界のデジタル革新は、ここ数年マーケットとしても注目されてきましたが、浦川さんはどのように捉えていらっしゃいますか。
浦川 2015~16年ぐらいから保険市場でデジタル革新という言葉が認知されることが増えてきて、「保険の未来はこうなる」といった議論もたくさんあったと思います。
しかし数年が経過した今日、保険業界にそこまで激震が走ったのかというと、そんなことはまったくない。自動車保険もドライブレコーダー特約※2やテレマティクス系の保険※3は出てきていますが、自動車保険の構造が劇的に変容したわけではないし、住宅など建物を中心とした火災保険の形もほとんど変わっていません。
※2自動車保険の契約をしている保険会社から、低コストで高性能なドライブレコーダーの貸出を受けることができる特約。ドライブレコーダーによって事故が起きた際の一部始終を撮影できるだけでなく、危険を知らせたり、緊急時に自動的に事故受付センターに通報してくれるなど、事故の際のサポートを受けられる点がメリット。
※3自動車に設置するカーナビやドライブレコーダーなどの端末から運転者の運転情報を保険会社が取得し、その情報を基に保険料を算出する保険。安全運転をすれば保険料を抑えられる。
保険は生活者の「楽しく安全に暮らしたい」という普遍的な願いに付随する産業ですから、おのずと変化も緩やかになる。これから5年、10年、15年といった時間軸で、気付いたらかなり変容していたというぐらいに、じわじわ変わっていくものなのかなと考えています。
ビジネスモデル、システム、人材を同時に変革する半アジャイル手法
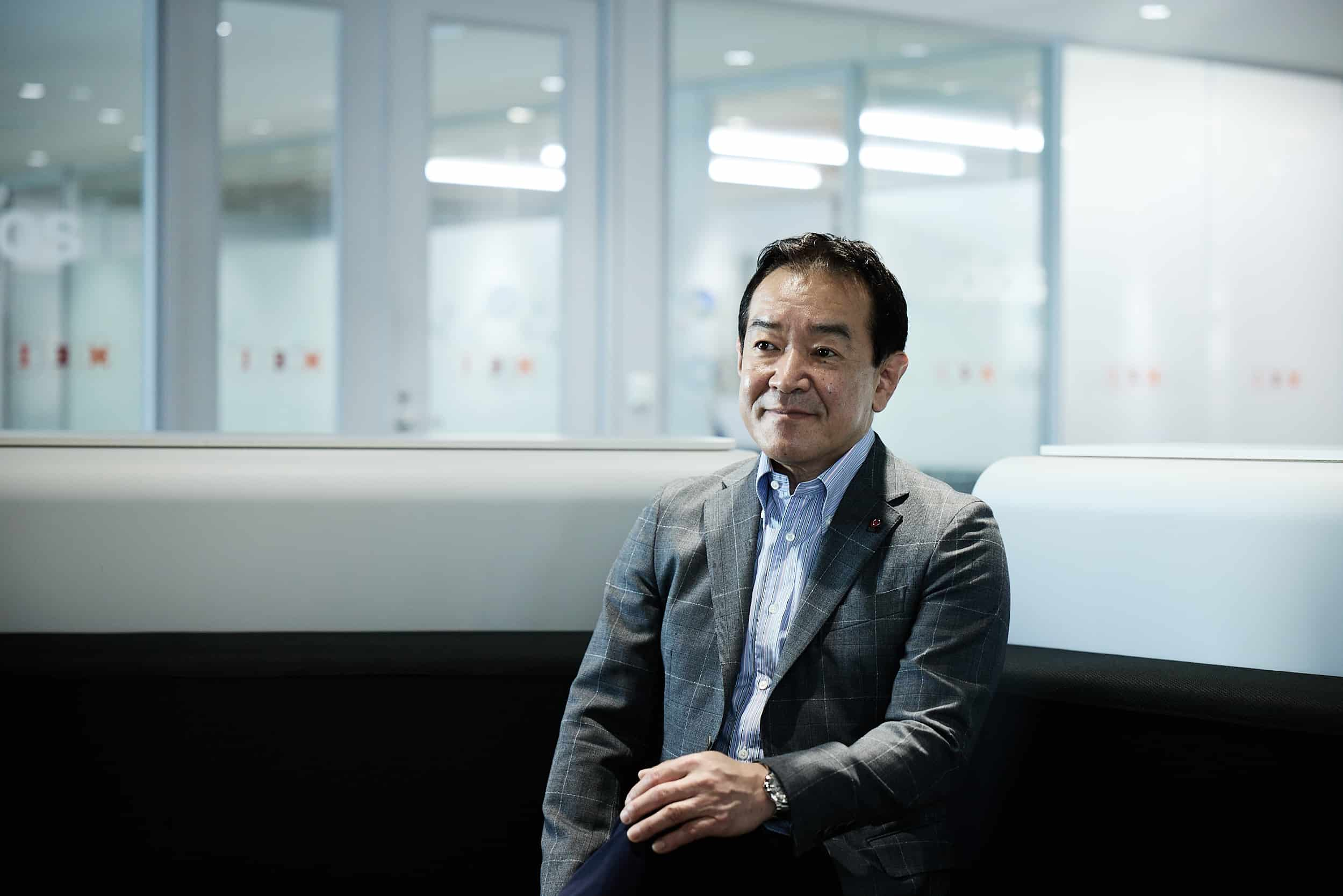
藤田 おっしゃるとおり、生活者にとっては保険そのものが変化している認識はないかもしれません。一方で、保険会社自体を支えるインフラなど、お客様から見えないテクノロジーの部分ではかなりの改革が行われていますよね。
浦川 そうですね。SOMPOホールディングスCEOの桜田も、「『急激には変わらないから粛々とやっていこう』なんて胡座をかいているととんでもないことになる」と、2016年ぐらいから社員に檄を飛ばしていました。
「我々は近い将来、保険会社ではなくなるかもしれない。それくらいの激変を見越して、自ら積極的にビジネスモデルを変革していくべきだ」と。それに付随して、変化するビジネスモデルを支えるシステムや人材を育ててほしいというのが、桜田から私へのオーダーでした。
なすべきことはいろいろありましたが、重要なのはビジネスモデル変革、システム変革、そして、人材変革。この3つの変革を同時並行的に進めていかなければ、保険会社は中長期的な時間軸での変革に耐えられないと気が付きました。
藤田 ビジネスモデルをデザインするにしても、それを支えるシステムが必要ですし、システムを稼働させたとしても、そこに対して人材が育成されていなければ実行できませんね。
浦川 この3つは完全に三つ巴です。ビジネスモデルだけ変革しても付け焼き刃で終わってしまいます。
藤田 CIOという立ち位置を考えても、最近はシステムの専門家というより、経営的観点でビジネスモデルの変革をリードしていくように、要求される役割が変わってきているように感じます。
浦川 それを一番実感したのは、「SOMPO-MIRAI」の開発過程でウォーターフォール型※4の限界に突き当たったときでした。
※4プロジェクトを各工程に分け、確実に工程を進めていく開発手法。テストを重ねて進めていくため、手戻りが発生した場合は手間や工数が余分にかかってしまう。
これまではビジネス要件を聞いて、システムとしてどう実装するのかを設計、開発、テストして提供するのがエンジニアの仕事でした。しかし現在は、変化が激しすぎてビジネス部門が一度要件を決めても開発途中に変更を余儀なくされる。これはアプローチを抜本的に変えなければなりません。
追加対応がいくらでも可能な、アメーバのようなブロック構造でシステムを作っておかないと無理だと。オーダーされたものをきちんとアラインして体系化したシステムを作っても、おそらく数年で崩壊すると思ったのです。
そこで「SOMPO-MIRAI」では、システム全体が疎結合化、マイクロサービス化されていくようなアーキテクチャを構想しました。要件がいくら変わっても実装できる基幹システムにしようと閃いたんですね。
藤田 テクノロジー人材がITの世界に入ってきたときは、いかに要件を構造化して、それを間違いなく動かすかが命題だったと思います。
一方で、「SOMPO-MIRAI」はダイナミックモデル、つまり動的モデルなので、それぞれのエリアというかパーツが、まるで人間の体の機能のように自立して動きながらも統制されています。
この発想は、製造業を得意としてきた日本企業には、かなり難しい命題になるのかもしれません。何かというと設計図を見せろ、答えを見せろという経営層に対して、「常に変わるものですよ」と言い切っていくのは勇気のいることですし、周囲の理解がどこまで付いてくるのかも気になるところです。
浦川 実は、そういった説明を周りにはあまりしていなくて、開発部門には「ウォーターフォールでがっちり作るぞ」と言っていたのです(笑)。ところが、要件定義や設計局面で次から次へと新たな要件が出てくるので、「各工程で100点を取って次の局面に進む」ということ自体に無理がある時代になってきたのだと感じ、裏である程度のバッファーを持っておくことにしたのです。
壮大なウォーターフォール・プロジェクトと見せかけて、実際には「半アジャイル」型の開発をしてきたというのが、足かけ8年にわたるプロジェクトの実態だったように思います。
藤田 アジャイル※5か、ウォーターフォールかという議論に終始して開発が進まないプロジェクトが多い中で、浦川さんはシステムがうまく機能することにフォーカスされた。そして、全体的には馴染みやすいウォーターフォール型を描きつつ、俯瞰的に見たときにはアジャイルで、つまり遊びがあるような形のアーキテクチャ・デザインをされたということですね。
※5大きな単位でシステムを区切ることなく、小単位で実装とテストを繰り返して開発を進める開発手法。これまで主流であったウォーターフォール型に比べて開発期間が短縮されるため、アジャイル(素早い)と呼ばれる。
こうしたマネジメント手法の秘訣は、読者の方も気になるところではないでしょうか。アジャイルの観点の人もウォーターフォールの観点の人も納得させながら開発をリードしたのは、非常に大きな実績だと思います。同じような問題で悩んでいる人に、どうアドバイスしますか。
浦川 専門領域になるので説明が難しいのですが、極めて単純化してお話すると、基本はウォーターフォール的にきっちり決めて、やれるところまでやるべきでしょう。やってみるとわかりますが、フルアジャイルは慣れが必要で少人数チーム向きなので、大規模開発には向いていません。ユーザー部門を中心に、追加仕様をいつでも取り込めるように誤解する人も多いですが、そんなことをしていたら予算と期間がいくらあっても完成しません。
「基幹系はこのぐらいの予算額であれば投資効果が出る」ということを経営に諮ってプロジェクト化しているわけですから、基本は一定のバッファーを持って計画を立てる。特に基幹システムでは絶対条件です。
そのうえで、余力を残しておく。例えば、要件定義や外部設計は85点しか取れない可能性が高いと読んでおき、残りの15%はバッファーの期間と予算として、要件の取りこぼしや追加仕様を可能な範囲で取り込めるように持っておきます。私が「半アジャイル」と言うのはそういうことです。
藤田 バッファーや遊びをどこまで持っておくのかは、究極のデジタル戦略、センスなのかもしれませんね。
浦川 そのとおりです。私も当初予算を多めに取っておいたのですが、いま思うと想定を超える額が必要でした。基幹業務をオープン系で再構築するという経験のないプロジェクトであったため、振り返ってみるとあらゆる作業を事前にリストアップし、工数、生産性を加味してプロジェクト計画を立案することは大変難しかった。経営会議で何度も「すみません、足りませんでした」と苦しい答弁をしながら、それでもプロジェクトの方向性に間違いがあったわけではなく、追加仕様や例外処理にかかる費用であることを納得してもらい、追加予算を数回程度取りにいきました。
藤田 いまの話で学ばせていただいたのは、プロジェクトの遂行においてはバッファーや遊びが不可欠であること、ウォーターフォールとアジャイルを俯瞰した「半アジャイル」型のデザインが有効だということ。
それでも予算オーバーしたときは、プロジェクトを諦めるか、縮小するかといった話になりがちですが、合理的な説明ができるのであれば、プロジェクトを再度進めることが可能ということです。浦川さんのチームに参加された方も、きっと多くのことを学ばれたのではないかと思います。
浦川 そうであれば嬉しいですね。私の中では進み続けたポイントが2つあって、1つ目はベースとなる設計思想とアーキテクチャに対する絶対的な自信です。これをやり切れば、保険マーケットの変化に対応できる基幹システムが必ずできる。そこはテクノロジー面でも、自分で確認しながら進めていきました。
2つ目は、このプロジェクトを断念すれば、現行システムを使い続けることになります。それでは今後のデジタル革新に、我が社が耐えきれないという思いがありました。
藤田 来たる保険マーケットの変革に、柔軟に対応できるインフラにはならないと。
浦川 ならないですね。多大なコストをかけ続ければできるかもしれませんが、非常に大きな経営の足かせになる。その確信があったので、プロジェクトを中断するなどの迷いは一度もありませんでした。
藤田 保険業界の顧客モデルは、ゆっくりと、しかし着実に変化しているという話がありました。保険会社がこれからもお客様にサービスを提供していくためには、どのような能力が必要になるとお考えでしょうか。
浦川 保険会社が持つべき能力は、シンプルに2つあると思っています。1つ目は、これまで培ってきた既存の商品、サービス、ビジネスモデルを、きちんとサステナブルにお届けし続けること。これらを望まれているお客様はまだたくさんいらっしゃいます。
2つ目は、新たなビジネスモデルに対応した商品を生み出すことです。「新たな」といってもバリエーションがあると思いますが、10年、20年をかけて緩やかに旧から新にシフトしていくでしょう。
この数年間、デジタル部門はPoC(概念実証)や本番実装を繰り返してきましたが、その多くは部分実装でした。例えば、問い合わせの部分をAI化するとか、コールセンターのFAQの仕組みをAI化して申し込みもスマホでできるようにするとか。全体の商品サービス、ビジネスモデルの中の一部分を切り取り、テクノロジーをはめ込んで加速化・省力化・多様化させてきたわけです。
これからは、保険会社の基幹業務に、AIなどの先進技術が次々と組み込まれていくことを想定しています。これまでに培った技術を段階的に統合化・再結合し、また新たな商品サービスに組み合わせていくことになるでしょう。この部分はあまりうまくいかなかったから元に戻そうとか、ここは非常にうまくいったから対象外にふくらませようとか。はめ込んでみたテクノロジーが、それぞれに進化や退化をしていくだろうと思います。
新旧のビジネスモデル同士で化学反応が起きることで、デジタル対応する部分がどんどん増えていくのだろうと。例えば、当社でも他社と同じく一部の保険プロセスでフルデジタル化※6を始めていますが、どこまで進化するかは未知数です。一番大事なのは、生活者=お客様の目線と利便性、お客様の体験価値につきますね。
※6契約申し込みから保険料の支払い、事故が起きたときの対応、保険料の受け取りまで、人といっさい対話せずにウェブ上で手続きを行えるようにすること。
ビジネスにテクノロジーを応用するために必要な3つのアイデア活用

藤田 顧客体験を向上させるアイデアは、これまでは営業、マーケティング、商品設計など、お客様に近い部門から生まれるもので、テクノロジーやIT部門とは遠い存在だと見られがちだったように思います。それが変わってきている。
ビジネスアイデアや新しい発想にテクノロジーを応用するのが、今後の保険業界の一つの命題になるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
浦川 アイデアを因数分解すると、3つに分けることができるのではないかと考えています。
1つ目は、ビジネスモデルそのもののアイデア。例えば、保険を複数の企業といろいろなサービス提携をして、一つのバンドル化されたサービスとして売るのが典型的です。サービススキーム、商品スキームとして、ビジネスモデルをデジタル変革、デジタル活用で大胆に生み出していくといったものですね。
2つ目は、商品やサービスそのもののアイデアです。直近の例では、自動車保険のドライブレコーダー特約が当たります。ハードウェアを保険商品の特約に埋め込んで、できるだけ事故が起こらないようにする発想です。自動車メーカーと連携したIoT関連の保険も出始めています。
3つ目はビジネスプロセスや事務のアイデア。帳票などの内部処理や顧客接点に関わるものです。Zoomで打ち合わせをしたら、そのまま連携して契約に結び付けられるとか、社内プロセスを簡略化して自動化し、AIに組み込んでいくとか。
これらを総括してアイデアとして考えるとすると、どうしても空中戦になってしまうので、どこからなら実現できるのかと足元を見ながらやっていくことが重要です。これは商品分野、これはビジネスモデル、これは事務プロセスに関するアイデアだということを常に頭の中で体系化しながら、できるだけ有機的にガバナンスしていくことが、アイデアの取り込みには必要だと思います。
藤田 アイデアも、プロジェクトと同じように、発想するだけではなく、実現することが大切ということですね。例えばアイデアをテクノロジーとして実現させていくためには、そのアイデアを図にする作業が必要になりますし、アイデアを実現させる設計士のような人材が重要になってきそうですね。
浦川 そうだと思います。組織ごとにミッションを分けてしまうと、ポテンヒット・エリアが広がることは実感しています。IT部門とデジタル部門を分けて設置している企業は多いと思いますが、この境目もできるだけ一体化して、コミュニケーションを密にしないといけない。少しポジションが重なってもいいぐらいの感じで人を交流させていくことが大切でしょうね。
アイデアの実装において、最も重要であり、忘れてはならないのはパーパス経営と考えています。大事なのはお客様ですから、お客様が当社に振り向きもしなくなるようなシステム開発をしてはならない。例えばIT部門は品質確認や検証にかなりの時間を費やしますが、スピードを重視するデジタル部門からは不満が出がちです。ただIT部門を通さずにデジタルアプリを本番リリースすると、本番障害を引き起こすなど、お客様にご迷惑をかけてしまうことになります。スピーディーにマーケットに投入したい気持ちはわかるけれど、スピーディーに欠陥のあるものを提供したら、取り返しのつかないことになるわけです。
だからIT部門とデジタル部門の双方が歩み寄ってコラボレーションし、「これがお客様にとって最適だ」というスピード感と品質を担保しなければなりません。お互いのやり方を食わず嫌いで敬遠しているところがありますが、そこは同じ技術者同士で、語り合えば落としどころは見出せます。
そのためにも両者をお見合いさせるというか、両方の良し悪しを知るコーディネーターのような人が必要になる。そういうハイブリッドな人材が不足するとギクシャクしますよね。
ムーンショットに欠かせない本物のダイバーシティ&インクルージョン

藤田 テクノロジーを活用するうえで、お互いに自由に意見や発想を言い合える、オープンコミュニケーションができる状態を作ることは非常に重要なのかなと思っています。
一方で、自由すぎる発想、つまりムーンショット※7という考え方があります。日本の産業界はこれが不得意で、笛吹けど踊らずといったところがある。歴史の長い保険業界で、いかにムーンショットが生まれる文化を作っていくか。これについてぜひ人材的な観点からご意見を伺いたいです。
※7前人未踏で非常に困難だが、達成できれば大きなインパクトをもたらし、イノベーションを生む壮大な計画や挑戦のこと。
浦川 これは構造が難しそうに見えますが、実はものすごくシンプルで、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)に尽きると私は思っています。
いまD&Iは用語として知らない人はいないぐらい定着していますが、実践できる人は限定的です。さきほどのITチームとデジタルチームの意見のすり合わせも同じことです。例えば、意思決定に際して3段階承認のプロセスを1週間がかりで進めるITチームに対して、デジタルチームは「Slackで議論すれば5分で済むじゃないか」という議論になるわけです。
これはいい悪いではなく、単に凝り固まったカルチャーの違いでしょう。承認プロセスが細分化されているのは責任分担を明確にすべきという過去の経験が積み重なったものだとするなら、「何がパーパスなのか」という視点で、プロセスを見直す。「Slackで決めるのなら、その決定プロセスを記録できるように社内規定を変えよう」といった形で、双方が合意できる方法を取ればいいはずです。それをせずに「こんなやり方をするチームと話す時間はない」と言い放っていたら、話は平行線になるだけです。
私はシステム開発の現場において、「いまさら」とか「その話は聞いていない」といった言葉は禁句にした方がいいと思っています。「その発想面白いね」「ちょっと聞かせて」。これがインクルージョンの始まりです。
藤田 世の中的に、ムーンショットを出すような尖った人材を大切にしよう、そういう人が活躍できるような文化を醸成していこうといった意見が増えていますよね。
浦川さんは、ムーンショットを打ち上げられる人と、若干そこに対立するようなコンサバティブな人、双方の立ち位置を考慮されている。尖った人がコンサバな人にも理解してもらえる形で動くことによって、双方が成り立つ関係性ができる。これが価値観や考え方、働き方のダイバーシティにつながるということですね。
浦川 多様性を認めることが多くの日本企業で障壁になっている理由は、オーソリティとルールによって会社の業務を規定してきたからではないかと。そのため、ムーンショットを打とうとした瞬間に、「そんなことをしたら事務規定違反になる」と言われてしまう。そのルールを撤廃するオーソリティがないと、日本企業は真面目だから人が動けないのです。
「これはおかしい」と思ったら、一定のオーソリティを持った人が関連部門を巻き込み、規定を変えにいく。そうすれば「なんだ、ムーンショットを打ってもいいんだ」ということになり、文化が変わっていく可能性があります。
藤田 リーダーシップ論にも近いところがありますね。
浦川 おっしゃるとおり。「それっておかしいよね」と気付き、関連部門を説得できるリーダーがいないと、その組織は永久に変わることができないし、できる人は辞めてしまうと思います。
これからの保険会社で求められるテクノロジー人材のあり方

藤田 最後にディスカッションしたいのは、時代に求められる人材の要件についてです。浦川さんは今後の保険業界で、どのようなテクノロジー人材が求められていくとお考えでしょうか。
浦川 まずは用語の整理をしたいのですが、テクノロジー人材とは、主としてIT部門の人材を指し、システム人材やIT人材と同義語と捉えています。ITを担当する人材の今後のあるべき人材像として、当社内では具体的に複数の専門職に分解し、先進技術領域も含めて定義しています。
最近ではDX人材やデジタル人材という表現も増えています。DX人材とは、デジタル技術を駆使してビジネスモデルをトランスフォームする、他社・他業界に業務提携を仕掛けられるレベルの人材で、会社の立ち位置、パーパス経営から見てDXを実践し、リードしていく人材と位置付けています。デジタル人材とは、ユーザーとしてビジネス遂行においてデジタル技術をフルに使い倒せる人材と位置付け、社員全員が身に着けるべきと捉え、精力的にスキルアップ施策を進めています。
テクノロジー人材に対する要件は急速に変化しています。昔は決められた要件定義を基に、コスト・納期・品質を保ってシステムを本番稼働させるのが仕事でした。現在は、新たな価値観やツール、AIによる機械学習工学などを身に付けながら、自分をアップデートできる人材が求められています。
藤田 アプリケーションはアップデートが当たり前の世界になっているように、テクノロジー人材もセルフアップデートが実施できることが重要なのですね。
浦川 冒頭で申し上げたように、普遍的な部分と劇的に変化している部分を見極めることが大切なのではないかと。普遍的な技術を捨てる必要はありませんが、従来のやり方にこだわっていると考え方が陳腐化してしまいます。品質は無論大事で外せない要素だけど、品質の高め方は時代によって変わるということです。
お客様に「保険」という真心を届けていくためにDXを推進する

藤田 今日は「Future of Insurers」というテーマで議論してきましたが、デジタル革新なくして未来の保険像はないと考えております。浦川さんは未来の保険業界に対して、どんな変化を期待していらっしゃいますか。
浦川 これは桜田の見解でもありますが、保険はなくならないとしても、保険業界はなくなるかもしれないというぐらいに考えておいた方がいいのかもしれません。
人が行動すると、何らかのリスクが生じる。保険は多くの場合、それを担保するサービス産業です。だとすれば、徹底的にホワイトレーベル化して、eコマースで何かを購入したらすべてのトランザクションに少額で保険が付くようになるかもしれません。このようなビジネスモデルに保険商品という概念はありません。保険は元々、サブスクリプション型のサービス形態に近いと思いますが、今後は保険が主体ではなく、付帯サービスとしての色が濃くなることも想定されるでしょう。
一方で、保険はインフラ事業として絶対に必要な存在です。弊社には、「人が好き」な人が多いです。使命感があって、どこかで台風や地震の被害があれば、我が事のように現地にすっ飛んでいく。稚内から沖縄まで支社を置いているのは、そういうことだと思うのですよね。
ですから保険業界には、Society5.0※8、サイバー空間とフィジカル空間の融合を地でいく業界であってほしいし、それをリードしていきたい。お客様に真心を届けるために、それ以外の仕事は徹底的にデジタル化していく。それが未来の保険業界の基本であり、「保険」という言葉をなくさないためにできることなのではないかと思います。
※8サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会。内閣府の『第5期科学技術基本計画』にて定義されている。
本対談の内容を基に描いた、人の生活に寄り添うための保険会社のあり方
Future of Insurers対談#3 DXの真髄から見る、保険業界のデジタルと人の心地よい関係





