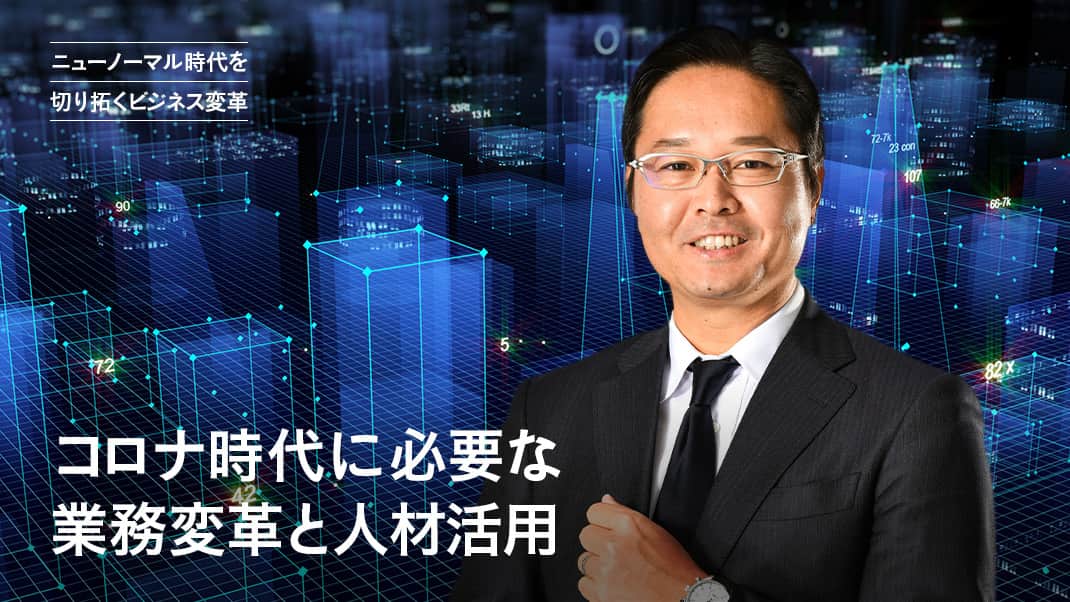梅田恵
日本アイ・ビー・エム株式会社 人事
ダイバーシティー企画担当部長
2008年から現職。女性、障がい者、性的少数派、ワークライフに注目した人事制度、プログラムの企画・開発を担当。主な実績として、フレックス短時間勤務制度、ホームオフィス制度、同性パートナー登録制度、障がい学生向け長期インターンシップの開発などがある。また企業内保育園を本社と幕張事業所に開設。

加藤あゆみ
日本アイ・ビー・エム株式会社 グローバル・ビジネス・サービス事業
戦略コンサルティング
シニア・マネージング・コンサルタント
新卒にてIBMビジネスコンサルティングサービスに入社(統合を経て、日本IBM)。戦略コンサルタントとして製造業や保険業界を中心に、M&A戦略立案・M&A実行支援、グローバル化戦略、組織改革・実行支援、ガバナンス戦略などの案件をリード。

岡村周実
日本アイ・ビー・エム株式会社 グローバル・ビジネス・サービス事業
戦略コンサルティング
アソシエイト・パートナー
さまざまな業界でパブリックセクターとプライベートセクターをつなぎ、両者の課題解決や新たなエコシステム創生を主眼に活動を続ける。
【座談会参加者】
- 梅田恵(日本アイ・ビー・エム株式会社 人事 ダイバーシティー企画担当部長)
- 加藤あゆみ(同グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略コンサルティング シニア・マネージング・コンサルタント)
- 岡村周実(同 グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略コンサルティング アソシエイト・パートナー)
- 参加学生(五十音順)
秋場玲美さん(慶應義塾大学)、阿部こなみさん(東京理科大学)、大塚夕奈さん(横浜市立大学)、北口智章さん(東京大学)、小梶 直さん(慶應義塾大学)、高原奈穂さん(慶應義塾大学)
読者、識者、記者が一緒に議論しながらテーマを深掘りしていくメディア「日経ビジネスRaise」——。2018年7月~12月にかけ「『ダイバーシティー社会』には何が必要か?」をテーマとしディスカッション企画が展開されたが、2019年1月、その議論を発展させるために「企業におけるダイバーシティー」をテーマにした座談会が開催された。Z世代の参加学生6名との対談に臨んだのは日本IBMの社員3名だ。同社・岡村周実氏をモデレーター役に、ダイバーシティーに関するさまざまな施策に取り組む梅田恵氏(バブル世代)、さまざまな国で多様な文化的背景を持つ多国籍のメンバーと共に働いてきた加藤あゆみ氏(ミレニアル世代)を迎え、それぞれの世代の経験も踏まえながら学生たちの疑問に答えていった。さらに後半では、グローバル企業であるIBMがダイバーシティーに対してどのような取り組みをしてきたのか、梅田氏と加藤氏に話を聞いた。
多様性をめぐる文脈の変化が起きている

岡村 今回の座談会は「企業におけるダイバーシティー」がテーマです。梅田さんはこの言葉をどう定義されますか?
梅田 もともとダイバーシティーは「Diversity and Inclusion」と、2つの言葉のセットで考えられていた背景があります。海外では5〜6年ほど前から「DiversityからInclusionへ」と徐々にシフトしています。Inclusionを直訳すると「包括・包含」といった意味になりますが、「目に見えないDiversity」とも言い換えられるかもしれません。従来のDiversityが性別や肌の色、障害の有無など目に見える違いに注目するものだったのに対し、Inclusionは「誰もが臆することなく自分の意見を言うことができ、それが尊重される職場環境」です。
岡村 弱者救済の文脈から企業のイノベーションを促す文脈へ、とも言い換えられそうですね。
梅田 そうですね。今は3カ月先のことすら予想するのが難しい変化の多い複雑な時代です。だからこそ、そこで働く一人ひとりが自分の考えを持ち、変化に対応し、自分らしく働き、お互いに尊重し合える働く環境がますます求められていきます。
岡村 さらに言えばInclusionであるからこそ、その環境に包括・包含される個々人の側にとっても、Inclusionされるために自らの価値や能力、経験値について説明責任を問われます。Diversity and Inclusionには企業・個人、両者にとっていささか「厳しい側面」がありそうです。加藤さんはいかがでしょう?
加藤 諸外国では生まれ・国籍が違うのは当たり前。その点から言っても、その対局にある日本では「Diversity and Inclusion」の理解促進が難しいかもしれません。例えば私のプロジェクトでは国籍・性別に限らず、多領域のプロフェッショナルが集っているため、一人のプロフェッショナルとして認めてもらうためにも、「自分が何のプロなのか」「自分が発揮できる価値が何なのか」を常に意識・発信していかなければ、Inclusionされません。厳しい側面はあるものの、発信力や個としての仕事力、短時間で信頼関係を築く力など、さまざまな力が養われます。
Z世代が抱える曖昧な不安と、3つのヒント

岡村 今日はZ世代の学生さんたちにもご参加いただいています。こうしてダイバーシティーの定義が変わりつつある中、不安に感じる面はありますか?
大塚 不安というほどではありませんが、多くの世代でそうであるように、私たちの世代間でも「何歳で結婚」といった“幸せのモデルケース”みたいなものが存在しています。「個人にも厳しい」「自分でその答えを見つけなければいけない」といったお話を聞いて感じたのは、「ならばこれから何にすがればよいのだろう?」という率直な疑問でした。
岡村 偏差値がいくつならこの大学に入れる、みたいなものもそうですよね。大人たちが敷いてきた「偏差値至上主義」的な日本の教育も、Diversity and Inclusionとは対局にある考えかもしれません。
高原 高校生活まで成績や偏差値が一つの指針になっていたので、大学入学と同時に自分のアイデンティティを見失う学生は多いと思います。一人で生きていくことに不安がある、といいますか……。
阿部 出産というライフイベントが不安です。私は生物学を専攻していて、研究、実験、論文といったことに割く時間がどうも多くなりがちで、将来的にそれをしながら結婚生活と子育てをできるのかどうか……。学校で研究されている先生方の人生はとても楽しそうですし、この道で生きていくのに迷いはないのですが、自分のためだけに生きるのが本当によいことなのかというささやかな疑問もあり、仕事と結婚・出産の両立という面でどのように生きていくのか考えています。
岡村 3名からいくつかのテーマが出ましたね。特に阿部さんのお悩みについて、梅田さん、加藤さんはどのように考えますか?
梅田 今、社会はどんどん変化していて、女性は今後ますます活躍できるようになっていくと思います。阿部さんのお悩みにしても産官学が連携した女性研究者育成の取り組みが始まっていますし、日本IBMでも子育てセミナーを開催すると3割くらいが男性で、男女問わず仕事・子育てを両立できる環境や支援が整いつつあります。これから皆さんが生きる未来はとても明るいので、まずは安心していただきたいです(笑)。
加藤 今後、日本もヨーロッパのような「18時以降に残業していれば能力が低いと思われる」働き方に変わっていくかもしれないですね。特に女性は、選択肢を選びやすい環境になりつつあるのではないでしょうか。もちろん男性にとってもワーク以外のライフの選択肢が増えていくことになると思います。
梅田 女性は結婚・出産を契機にしてワークとライフの選択肢を迫られてきましたが、反対に男性にはその機会が長らく与えられてきませんでした。企業以外で働くことの選択肢や、働く場所なんかも選べるようになるでしょう。それには自分の軸を持つことが重要。将来が不安なみなさんのヒントになるかもしれないのが、椎名武雄さん(日本IBM社長・会長・最高顧問などを歴任、2010年相談役退任)の言葉です。「ダイバーシティーを進めていくのには“3つのJ”が必要」というもので、Jとは自立と自律、そして自信。すなわち「自分の足で立ち、自分を律することができれば、それがやがて自信になる。そして、自信があれば新たなことにチャレンジできる」という意味です。
新時代に向けた日本版リーダーシップ論

岡村 Diversity and Inclusionの社会で「個」として生きていくのに、示唆に富んだ言葉だと思います。「3つのJ」が実現できない会社ならば辞めてしまえばよい。それを求めて海外へ行くという選択肢もありえる。さらにいえば「3つのJ」は多様化社会における新しいリーダーシップのような気もします。北口さんは高校のとき「特定のテーマについて参加学生が大使となり、各担当国の立場から国連さながらに議論・交渉・決議採択を行う活動」である「模擬国連」をご経験されたそうですね。おそらくそこでもリーダーシップが求められたと思いますがいかがでしたか?
北口 議論・交渉・決議採択にあたって、確かにリーダーシップが求められました。私がその場で特に注意したのは「能動的な受け身」。まずは相手の意見を受け止める、そのうえで自分の主体性を発揮しながら工夫を加えていく。調和を作るためのリーダーシップだったとも言えます。
高原 実は私も北口君と同じ模擬国連に参加しています。そのとき北口君は論理重視、私はムード重視でグループの議論をまとめました。幸いにして北口君も私も同じ賞を受賞したのですが、リーダーシップにもそうした個性のようなものがあるのでしょうか?
加藤 リーダーシップのスタイルにも個性が出ると思うので、意図的に使い分けられるようになるといいと思います。海外で仕事をしていると日本人は若く見られがちで、それがコンプレックスでした。特に若手の頃は、相手に対等に見てもらえるよう、意識的に海外でのふるまい方は変えていました。
梅田 自分が働いていて思うのは、能力が引き出される上司はこちらが多少稚拙なことを言っても、「その視点、面白いね」といった具合によいところを具体的に述べて入り込んできてくれます。リーダーシップは「黙ってついてこい」的な旧来型アプローチだけではなく、多様な価値を持った人をどのようにまとめていくかが問われてきていると感じます。
加藤 そうですね。リーダーシップに正解はなく、いろいろなかたちがあって当然だと思います。自分がどういうリーダーシップの色を出したいのか一度考えてみてもよいかもしれません。また、日本人は「リーダーシップを取るのが苦手」だと考えられがちですが、日本人の特性を活かしたリーダーシップもあると思います。例えば、「調和を大事にする日本人は、自分の意見を言わない」と指摘されることが多々ありますが、視点を変えれば「いろいろな人の意見を受入れ、新たな調和・価値を生むことが得意」とも言えます。また、日本人は「計画を作り、着実に進めていく」ことも得意なのではないかと思います。うとましく思われるケースもあるかもしれませんが、それらを活かしていけば日本流リーダーシップが確立されていくかもしれません。
岡村 「多様性」の議論は本来、企業だけでなく、家庭・コミュニティーなどさまざまな文脈で考えていくことに意味があります。この日の座談会では、その大切さを共有できたのではないでしょうか。座談会の最後に参加学生の感想を聞いてみましょう。
「自分が動くことで拓ける未来があると感じた」(小梶)
「人と人の間に多様性がある。コミュニケーションを取ることの重要性を感じた」(阿部)
「女性・人種といった分かりやすいラベリングでまとめるのではなく、一人ひとりの個性にまで掘り下げて語ることが大切」(北口)
「ダイバーシティーは自分が当事者。自分から第一歩を踏み出したい」(大塚)
「強烈な原体験がないことにコンプレックスを感じていたが、Inclusionすることの大切さを学べた」(高原)
「自分も多様性の一部であると発見した」(秋葉)
多様性を力に変えてきたIBMのDNA

学生たちとの対話を通じて、日本IBMの梅田さんと加藤さんは何を感じたのだろうか。座談会後、IBMのダイバーシティーへの取り組みや、学生たちへの印象について聞いた。
——現在、IBMはダイバーシティーをどのように考えているのでしょうか?
梅田 日本企業はどこも“ダイバーシティー”に熱心になっています。それに対してうれしさを感じると同時に、世界各地で社員を雇用し、世界で一貫した考えを持つ「ワークフォース・ダイバーシティー」(人材の多様性)で長い歴史を持つIBMは、「機会均等への社会責任」「管理者層の多様性の促進」「文化的相違の受容と認知(民族的マイノリティー、多言語、個人的な相違)」「女性の能力活用」「障がいのある人々およびLGBT(レスビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー)の能力の最大化」「ワーク/ライフ・バランス」など、あらゆるダイバーシティーのトピックで、そうした企業を常に牽引していく“先駆け”でなければならないと考えています。
日本IBMにおける「IBM Diversity」の具体的な取り組み(一部)
グローバルIBMの中で「女性社員の割合が世界最下位」「管理職に占める女性の割合がたった1.8%」……。女性活躍支援が進んでいると自負していた日本IBMにそんなショッキングな事実が突きつけられたのは1997年。1998年に日本IBMは“女性のさらなる活躍支援”を宣言し、社員の代表者からなる「Japan Women’s Council(JWC)」の活動をスタート。女性社員自らが女性のキャリア課題を分析し、在宅勤務制度など解決策の提案を行なっています。
○障がいのある人々への取り組み
情報アクセシビリティー向上の観点から視覚障がい者・聴覚障がい者を支援する技術の研究開発やソフトウェアの提供などを実施。また次世代の障がい者が働きながらIT、ビジネスの実践的なスキルを身につけられるインターンシッププログラム「Access Blue Program」を展開中です。
○LGBTへの取り組み
2004年にLGBT当事者による委員会を設置。2008年にはLGBTに対する積極的支援を社内外へ宣言しました。2012年にはNPO・国際NGOと共に任意団体「Work With Pride」を立ち上げ、「LGBTと職場」をテーマとした活動を定期的に行っています。
梅田 ダイバーシティーに関する取り組みをいろいろ行っていますが、いずれの活動もまだまだ発展・強化の余地があります。例えば、「女性活躍支援」では今年からあらためて各部門から選抜してもらった女性管理職候補者の育成プロジェクトを実施しています。LGBTにしても国内の施策は始まったばかりなので、これからも拡充していく必要があります。
——ダイバーシティーの各種取り組みにIBMがこれだけ意欲的に活動できるのはなぜですか。
加藤 IBMは元より働き方の多様性や変化に前向きに取り組んできた歴史があります。「世の中にないものを作る」「新しいマーケットを作る」というDNAがあり、「外から賛同者を呼び、多様性を融合させ、課題を解決する」ことを実践してきました。ダイバーシティーの世界でも、その歴史・DNAが受け継がれていると言えるのではないでしょうか。
世代を超えて求められる個の力

——梅田氏はバブル世代、加藤氏はミレニアル世代、そして参加学生はZ世代。座談会では世代を超えた議論が交わされましたが、梅田さんは多様性の理解において世代間の違いを感じることはありますか?
梅田 私はまさしく「大量採用の時代」に入社しています。しかし私よりも下の世代では徐々に採用が絞られ、若者が会社の中のマイノリティーになってしまい、彼らが意見を言いにくい時代が長らくあったと思います。我々バブル世代は、上司と部下の関係、あるいは会社と個人の関係において常に時代の変化を意識し、若者たちが世代を超えて刺激し合える機会を提供し、応援する必要があると考えています。
——岡村さんを含め、多様性に関する先進的な取り組みをしてきた3名は、真剣に議論する学生に対し、概念的な説明と具体的な事例を交えながら的確なアドバイスを送っていました。社会を取り巻く厳しい一面を忌憚なく指摘しつつも、その奥底には学生に対して希望も与える温かい気持ちもあったのではないでしょうか。最後に、ミレニアル世代の加藤さんから、Z世代の参加学生へメッセージをお願いします。
加藤 私たちの世代でもダイバーシティーについては表面的な議論に陥ってしまいがちですが、高い視座からダイバーシティーを意識した姿がとても印象的でした。もちろん社会に羽ばたいていく前の段階ですし、Z世代としてこれからの時代を生きていくのには不安も生じるでしょう。でもDiversity and Inclusionにより「個」が評価されるこれからの社会は、きっとみなさんの働き方や人生を豊かなものにしてくれるはず。個を磨いていけば、輝かしい未来が待っているはずです。