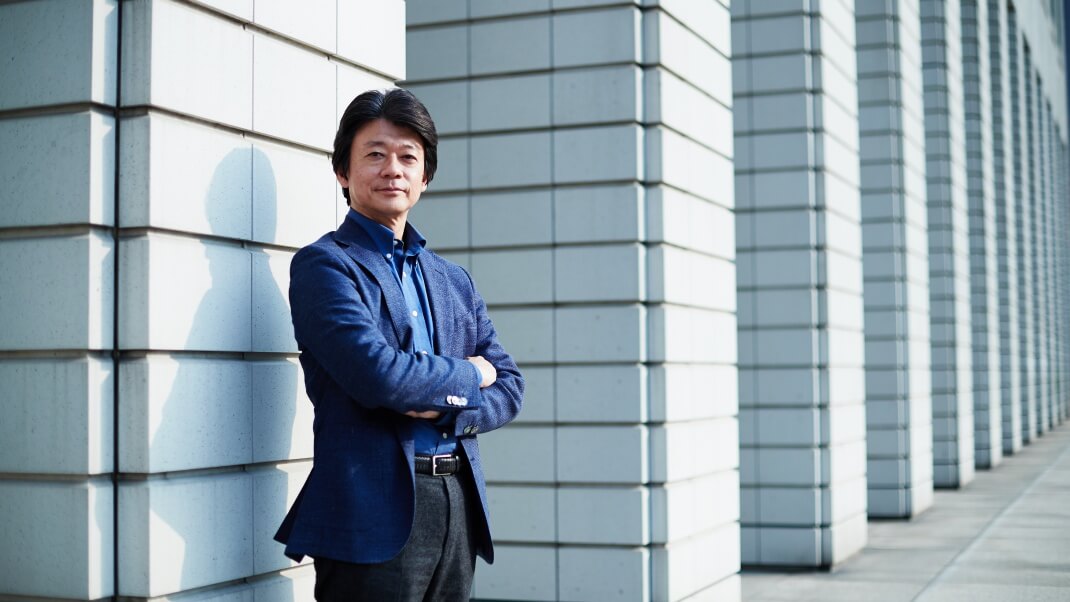若松 幸太郎
日本アイ・ビー・エム株式会社 グローバル・ビジネス・サービス事業 インタラクティブ・エクスペリエンス事業部 アソシエイト・パートナー
国内大手広告代理店及び、国内大手通信会社のデジタルマーケティンググループにて、SP/O2O/ソーシャル/マス媒体を絡めた大規模プロモーション、オンラインキャンペーン、デジタルチャネルの戦略構築から施策実施、運用管理など、様々なデジタルマーケティングのプロジェクトを経験。特にデマンドジェネレーション(リードジェネレーション、ナーチャリング、クオリフィケーション)領域については多くのプロジェクトを経験し、販売をゴールとしたマーケティング施策においてPDCAプロセスを活用し、マーケティングから販売にいたるトータルの設計に基づいた活動を数多く支援。近年はマーケティングオートメーションを活用したデジタルマーケティング領域を強みとして、大手MAベンダーのMarketoの日本法人立ち上げに関わり、同社取締役も経て現在に至る。
デジタル・トランスフォーメーションを社内でどのように推し進めるか解説した前回に続き、今回はそれと切っても切り離せない関係にある「現場の意識」をテーマにお話ししたいと思います。
「現場の意識」をスイッチせよ
当然ですが、あなた1人のがんばりでデジタル・トランスフォーメーションは成功するはずもなく、多くの現場の人たちを巻き込む必要があります。つまり、デジタル・トランスフォーメーションに不可欠な「テクノロジー」を日々使っている現場の人たちと、いかに上手に付き合っていくかがポイントです。
そこでまずやらなければならないのが、意識の切り替えです。テクノロジーを導入する際、「現場の要望をすべて実現しよう」と頑なに考えるのではなく、提供されたテクノロジーに「自社の業務や仕事のやり方を合わせよう」と考えてほしいのです。
「せっかくデジタル・トランスフォーメーションに取り組むのに、なぜ自社の要望を諦めなくてはいけないのか」
そういった声が聞こえてきそうです。しかし、私がこう申し上げるのには明確な意図があります。
なぜなら、いまは企業の要件に合わせたシステムを「1から開発」するのではなく、専門領域に特化したツールを「利用する」時代になったからです。自社システムの開発を目指して自社の知見のみで試行錯誤を繰り返すよりも、専門領域に特化した企業が提供するシステムを導入した方が、さまざまな企業の知見が反映されている上、導入スピードも圧倒的に早いのです。
デジタルネイティブ企業のノウハウが反映された既製品を活用
洋服に例えるなら、オートクチュールではなく既製品を買うということと同じです。
私もスーツをよくオーダーするのですが、確かに自分の体型にぴったりと合うスーツは非常に着心地がよいものです。しかし、デジタル・トランスフォーメーションの場合は、そうした“フィット感”が、時にマイナスに作用することが多々あります。
ご存知のとおり、デジタルの波はものすごいスピードで押し寄せ、日々進化しています。自社システムを1から作ると、いざ完成した時にはすでに古い仕組みになってしまっている可能性もあります。また、それまでデジタルを扱い慣れていなかった企業が必要な要件や機能を考えるよりも、デジタルネイティブな企業の要望が多く詰まり、進化を遂げているシステムの方が結果的に使い勝手が良いのです。
また、今では誰もが持っているスマートフォンですが、2010年代より前にこうしたツールが浸透することを、一体誰が予測していたでしょうか。
ある著名な経営者が、「消費者に、何が欲しいかを聞いてそれを与えるだけではいけない」「製品をデザインするのはとても難しい。多くの場合、人は形にして見せてもらうまで、自分は何が欲しいのかわからないものだ」といった趣旨のことを語っていました。
これはデジタル・トランスフォーメーションにも同じことが言えます。今まで経験したことのない取り組みに、希望を挙げて考えられる機能を追加しても、結果的に本当に欲しかったものや、必要なものではなかったりするものです。
ミニマムさに宿る、成功のカギ
そして、もう1つ気をつけなければならいのは、欲張ってシステムの機能をむやみに増やしたり、あまり使わない機能に固執してはいけないということです。
テレビリコモンを思い出してください。ほぼ毎日使っているのに、すべてのボタンの配置や機能を思い出せる人はほとんどいません。なぜなら、結局普段使っているボタンや機能は、限定されているからです。
デジタル・トランスフォーメーションに話を戻すと、みなさんはデジタル・トランスフォーメーションを推進し、日々のオペレーション業務のムダから解放されることも期待しているかと思います。
しかし、年に数度しか使わないような機能までシステムに追加したいと考え、それを無理やりにでも実現させようとすると、そもそもの取り組み自体が失敗してしまう恐れがあります。
なぜなら、今主流のSaaS(ベンダーのクラウドをベースに、ソフトウェアを提供するサービス)の場合、頻繁におこるバージョンアップ時に弊害が出る危険性が高く、そのカスタマイズに莫大な費用と期間を要します。年に数回しか使わない機能のために、多額の費用をかけて開発を行って、サービスインが数ヶ月遅れる上、その後のバージョンアップについていけなくなるなど、どう考えてもメリットが見当たりません。
とにかく、「あるがままのテクノロジーを受け入れる」ことが、デジタル・トランスフォーメーションの成功には重要です。
その証拠に、現在のSaaS製品は「グローバルスタンダード」で作られています。 世界中の企業が使いやすいようにデザインされている製品の方が、よっぽど汎用性が高いはずですし、それが使いにくいというのは、実は現在の業務のあり方そのものに改善の余地があるケースもあるのです。
デジタル・トランスフォーメーションによって高度な仕事をスマートにできるようになるはずが、専門領域に特化した「既製品に合わせる」という意識がないばかりに、全く逆の結果になっては本末転倒です。
だから私は、
「その機能って、いつ使われていますか? 」
「使用頻度が低いモノ(機能)の実現より、多くの企業が使いやすいと考え進化しているやり方を実践しないと、デジタル・トランスフォーメーションの意味がないですよ」
とお客様にいつもお話ししています。
いま、流行っている服を、「すぐ」に「安く」着る。そして、その服を世の中のアップデートに合わせて「アレンジ」する。
デジタル・トランスフォーメーションの成功を目指し、現場の意識をスイッチさせましょう。
photo:Getty Images