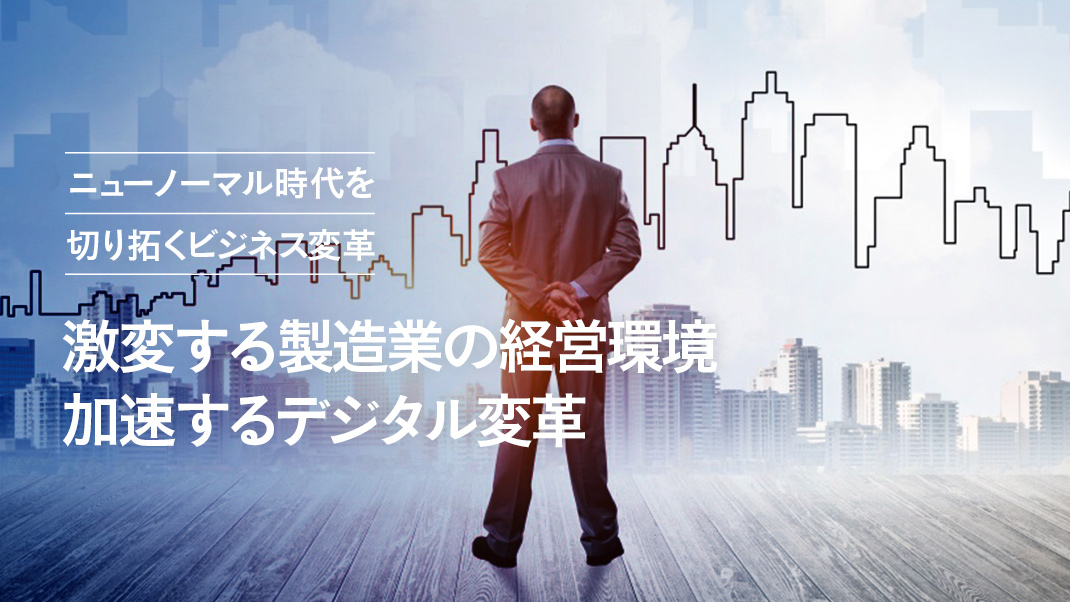デジタル・トランスフォーメーションについて論じた前回に続き、その成功に必要なポイントを、数回に分けて述べたいと思います。今回はデジタル・トランスフォーメーションを推し進めるにあたって、「経営陣をどう納得させるか」が主なテーマです。

若松 幸太郎
日本アイ・ビー・エム株式会社 グローバル・ビジネス・サービス事業 インタラクティブ・エクスペリエンス事業部 アソシエイト・パートナー
国内大手広告代理店及び、国内大手通信会社のデジタルマーケティンググループにて、SP/O2O/ソーシャル/マス媒体を絡めた大規模プロモーション、オンラインキャンペーン、デジタルチャネルの戦略構築から施策実施、運用管理など、様々なデジタルマーケティングのプロジェクトを経験。特にデマンドジェネレーション(リードジェネレーション、ナーチャリング、クオリフィケーション)領域については多くのプロジェクトを経験し、販売をゴールとしたマーケティング施策においてPDCAプロセスを活用し、マーケティングから販売にいたるトータルの設計に基づいた活動を数多く支援。近年はマーケティングオートメーションを活用したデジタルマーケティング領域を強みとして、大手MAベンダーのMarketoの日本法人立ち上げに関わり、同社取締役も経て現在に至る。
デジタル・トランスフォーメーションを進めるために
デジタル・トランスフォーメーションの必要性を真っ先に感じ始めるのは、大抵は現場です。その場合、まず、経営陣にその遂行について承認を得なければなりません。承認なしには、ヒト(意識、アプローチ)、モノ(デジタルツール)、カネ(投資に必要な資金)など、デジタル・トランスフォーメーションに必要不可欠な要素が揃わないからです。
では、どのようにすれば経営陣にデジタル・トランスフォーメーションの意義を理解してもらい、賛同してもらえるのでしょうか。
経営陣を説得するには、競合他社の成功事例や数的根拠を用意するのが鉄板といわれています。しかし、すでに世に出回っているのはいわゆる“チャンピオンデータ”であり、そうした事例や数字を自社に当てはめるのはいささか危険な匂いもします。なんとか当てはまりそうなデータを根拠に資料をまとめて経営陣に説明したとしても、大抵はどっちつかずの曖昧な反応が返ってきたうえ、さらにハードルの高い宿題をもらい、それを繰り返して次第に心が折れるという話もよく聞きます。
なぜ、経営陣はデジタル・トランスフォーメーションについて賛同、承認してくれないのでしょうか。
頭で“理解”させるだけでは、GOサインはもらえない
人は自らの経験や考え方をもとに意思決定を行います。企業の経営陣もそのようにして、会社を成長させてきた方々でしょう。
ただし、ベンチャーやスタートアップを除く大抵の経営陣は、50代以上のベテラン社員がほとんどです。彼らが現場の最前線にいた時代には、今ほどデジタルが身近な存在ではなかったこともあり、デジタル・トランスフォーメーションは「未知の領域」といっても過言でありません。
「従来のマーケティングスタイルから、デジタルマーケティングに切り替えましょう!」
こうした部下の主張に対して、その有用性を頭では理解しながらも、経験のないものに対して腹落ちしていない経営陣も多いのではないでしょうか。こうした状態ではどれだけ他社の成功事例や数的根拠を示しても、「やらない理由」を挙げられるのは想像に難くありません。
そこで、先述したように「共感アプローチ」を提言したいと思います。
明確に認識していないが、経営陣を含む誰もがすでに体感している「デジタルシフト」例を示してみましょう。例えば、皆さんが経営陣に対して行うプレゼンテーションで、このようなスライドを挿入してみるのはいかがでしょうか。
昔の通勤風景
今の通勤風景


これを見ると経営陣は、「昔は通勤時に新聞を読んでいる人が多かったが、確かに今は若い人だけではなく、普通のサラリーマンですらみんなスマホでニュースを見ている」と考えるでしょう。こうしたビジュアルは、新聞購読に関する推移データを見せるよりも、よっぽど共感してもらえるはずです。
言うまでもなく、経営陣はこれまでに数多くのビジネスシーンで困難な状況をくぐり抜けてきた、いわば“百戦錬磨の経験者”です。
デジタル・トランスフォーメーションをはじめ、そうした彼/彼女らになじみのない物事に関して承認を得る時は、理論武装するだけではなく、共感を得るのも有効でしょう。今やデジタルツールはすべての年代の人々に関わり深いものですので、共感アプローチを行う際のヒントが、必ずどこかにあるはずです。
次回は、デジタル・トランスフォーメーションの推進について、特にヒト(意識、アプローチ)の観点から論じたいと思います。
photo:Getty Images