※新型コロナウイルスの拡大防止に最大限配慮し、写真撮影時のみマスクを外しています。

宮田 大輔
日本アイ・ビー・エム株式会社
IBMコンサルティング事業本部
インタラクティブ・エクスペリエンス事業部
カスタマー・ストラテジー&プロセス
パートナー
20数年にわたり大手日本企業・海外企業のマーケティング、研究開発、商品開発、サプライチェーン、IT運営等の変革支援に従事。現在、IBMインタラクティブ・エクスペリエンス事業部にて顧客フロント領域の変革サービスのリーダーとして、構想策定・顧客体験デザイン・組織設計・プロセス変革・グローバルWeb/ECプラットフォーム構築・マーケティングソリューション導入・運用支援など多岐にわたるプロジェクトを統括。

中矢 徹
日本アイ・ビー・エム株式会社
IBMコンサルティング事業本部
インタラクティブ・エクスペリエンス事業部
CRMコンサルティング
アソシエイト・パートナー
ERP導入コンサルタントとしてキャリアをスタートし、大手電機メーカーを中心にシステム導入経験を積んだ後、CRMコンサルタントに転向。以後、20年にわたりCRM領域のコンサルティングに従事し、現在に至る。CRM戦略策定、顧客情報の統合、データ分析に基づくマーケティング、営業改革、コンタクトセンターやデジタル・チャネルを組み合わせた顧客接点改革など、CRMに関わる業務領域において、構想からシステム導入、定着化まで一連のライフサイクルをプロジェクト・マネージャー、プロジェクト責任者として推進。

高荷 力
日本アイ・ビー・エム株式会社
IBMコンサルティング事業本部
インタラクティブ・エクスペリエンス事業部
戦略コンサルティング&デザイン
アソシエイト・パートナー
国内大手広告会社で、自動車など多様な業界のブランド・販売戦略、事業・商品開発業務などに従事。2003 年から生活者の消費行動、および心理を研究する専門部門に所属。生活者心理の変容を起点に事業・サービスのアップデートを支援する共創プロジェクトを多数推進し、現職に転身。2020年4月から新型コロナの市場影響を予測する活動を通じて、多様な業種のお客様の次世代戦略推進をご支援している。また、2021年9月末には、IBM Future Design Lab.の活動として、第2回目となる生活者調査を実施した。

高田 晴彦
日本アイ・ビー・エム株式会社
IBMコンサルティング事業本部
インタラクティブ・エクスペリエンス事業部
パートナー 兼 alphabox マネージング・ディレクター
国内コンサルティング会社、総合広告代理店グループを経て現職。カスタマーエクスペリエンス全体の戦略設計を起点に、サービス開発・業務改革・プラットフォーム構築・グロースハックなど、顧客フロントの変革、マーケティング領域のデジタル・トランスフォーメーションに求められる一連のコンサルティングとソリューションを提供。日本IBMと広告代理店ADKとの戦略的協業体「alphabox」の共同代表を兼務。

若松 幸太郎
日本アイ・ビー・エム株式会社
IBMコンサルティング事業本部
インタラクティブ・エクスペリエンス事業部
パートナー
国内大手広告代理店、および国内大手通信会社のデジタル・マーケティンググループ、大手MAベンダーの取締役を得て現在に至る。多様なバックグラウンドを活かし、さまざまな角度から企業のデジタル・マーケティングやセールス領域の課題解決を支援。近年は、データの収集からサイロ化された既存データの活用支援や、ニューノーマルに即した顧客接点の再構築など、マーケティング領域を軸としたデジタル・トランスフォーメーション領域を強みとしている。
コロナ禍で多くの企業は急速なDXに迫られている。同時に、生活者の消費意識や、求める商品やサービスに対する期待もすさまじい勢いで変わっている。そのスピードに対応するべく、企業はどのようなビジネスの再構成(リインベンション)戦略が求められているのか。日本アイ・ビー・エム(以下、IBM)でマーケティングや顧客体験のエキスパートとして活躍する5人が語り合った。
コロナ禍でのデジタル・マーケティングは、生活者の納得度をいかに作るかが大切

宮田 IBMインタラクティブ・エクスペリエンス事業部では、2020年初にCMO(Chief Marketing Officer、マーケティング最高責任者)を対象にしたグローバル調査レポートにて、顧客体験領域の変革は、マーケティングから事業成長を考えたものに変わっていくであろうという示唆を提示しました。その後、コロナ禍で顧客体験の変革も加速し、ドラスティックになっています。本日はそうした背景を踏まえて、今後、日本企業における顧客体験はどうなっていくのか、各領域の第一人者のみなさんと議論しながら理解を深めていきたいと思います。
まず、IBMとして「生活者動向・DX 受容性調査」を行った高荷さん、最近の消費者の動向について、どのような知見が得られたのでしょうか。
高荷 調査は2020年8月末と2021年9月末に、2回実施しました。20〜70代の男女2,064名。日本の人口分布に合わせた数になっているので、日本の縮図系が見える調査内容になっています。
注目していただきたいのは、「日頃の生活や消費に対する考え方」。コロナ禍で自由に外へ行けなくなったことで、必要なものは「所有したほうが安心」という意識が高まっています。また、お金をセーブしたい意識はありますが、単純に安く買いたいのではなく、「実際に試すなど納得してから購入を決めたい」という意識が強いことがわかりました。
今後、デジタル・マーケティングの領域は、生活者の納得度をどのように作っていくのかが大きなポイントになるでしょう。また、「自分に合った商品、サービスを提案してほしい」というパーソナライズへの欲求も、今後も強くなりそうなので、顧客体験の最前線の一つのテーマになってくると思います。
高田 直近、alphaboxではカスタマー・エクスペリエンスに関する別の調査(alphabox CX Watch)を実施しましたが、その調査結果においても、商品選択の際に会社の同僚、友人・知人など「周りの人の情報」が情報源であるという割合が低下している結果が出ています。
これは周りの人の情報をあてにしなくなったというより、コロナ禍で他者と関わりを持つ時間が減ったり、関係が薄くなったりして、以前はリアルの場で意識せずに収集できていた知識や情報が減ったということでしょう。
このような受動的に入ってくる情報が減っている環境下では逆に、自分に合った方法やタイミングで納得感のある情報を企業から提案してもらえることは、確かにニーズとしてさらに高まっていくでしょうね。
高荷 我々の調査である「ネットやデジタル・サービスの活用に関する項目」でも、「ネットとリアルの“いいところ取り” をしたい」が73%と一番強かった。さまざまな調査結果に出ていますが、「ネットに特化したい」という人は約30%なんです。「リアルに戻りたい」という人も約20%。でも、両方のいい所取りをしたいという人は7割を超えるわけです。
また、購入の決定に際して、「商品を試したい」「人の反応を知りたい」などが大きなカギになっていて、店舗を単純に持っていることではなく、意思決定に慎重になっている生活者に対してどう体験設計で応えられるのかが重要になっています。そういう点で、IBMとしての強さが発揮できるといいですね。
高田 生活者のニーズが実にさまざまですので、一人ひとりに合った体験を踏まえたチャネル設計が重要ということですよね。例えばリアルに強みを持っていた企業の視点で言うと、デジタルでありながらも、どうしてもそのプロセスにリアルを組み入れて差別化したくなります。ところが生活者視点では、デジタルで情報の入手を始めた場合は、その後の購入やサービスまでデジタルで完結することが自然ですので、途中で店員が出てきてもかえってストレスが高まってしまうケースがよくあります。
なので、一律に「この領域はデジタル、この領域はリアル」や、「自分たちの強みを活かすために、入り口はデジタルでも最終的にはリアルで」などと決めたりするのではなく、自分にとってストレスフリーなチャネルを、生活者自身が選択できることを前提にしたコミュニケーションが必要ですね。
高荷 そうした傾向をバックボーンで支えているのが、次の質問だと思います。「インターネットの普及やIT技術の進化により、さまざまな製品やサービスが高度化していくという見通しが広がっています。このような潮流について、あなたの気持ちに最も近いものを1つお選びください」という質問(5段階選択)です。「積極的に受け入れたい」「やや受け入れたい」の合計は44.4%で、ほぼ半数。「どちらともいえない」という態度保留層が43.9%でした。
態度保留層の理由ははっきりしています。「使い勝手が悪い」ということと、「個人情報データを取られるのが怖い」ということなんです。この2つのポイントが解消されれば、ほぼ9割の人がDXによるサービスの高度化を受け入れようとしているわけです。高田さんの話にあったように、デジタルで完結した体験設計でも、その体験の納得度が高ければ、それが業界やサービスのネクスト・スタンダードになりうる。そういうふうに顧客体験の最前線が変わっていっていますよね。
新たな顧客体験を提供するため、顧客情報を活用してCXもEXも高める
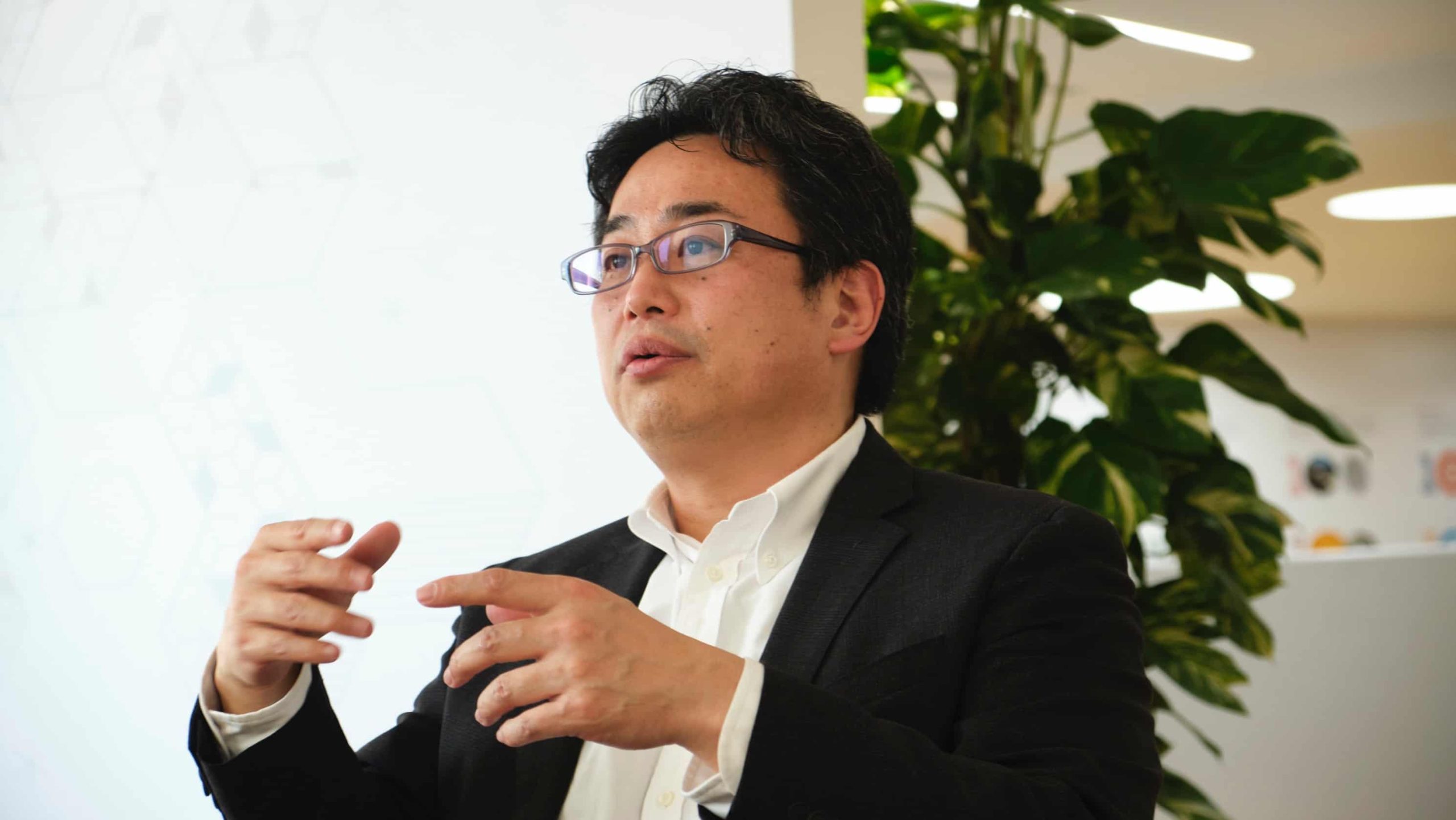
宮田 消費者の変化に対して企業がどうアプローチしていくべきかは、今後の顧客体験の取り組みの一つの観点です。我々がご支援しているお客様の中で、そのような取り組みをしていらっしゃるお客様の事例を紹介してください。
若松 第一生命保険さんのミラシル・プロジェクトですね。ただ、コロナがきっかけになっているわけではありません。コロナ以前から顧客と対面で会いづらくなったという課題がありました。ライフスタイルや家族構成が多様化し、かつ、いろいろなチャネルが増え、若い人たちも「リアルで会いたくない」と考える人が増えたからです。それをなんとかしなければという思いで、第一生命保険さんのプロジェクトが始まりました。
高荷 保険の営業職員のリソースも活かしながら、同時にデジタル接点も作り込んでいますよね。そこがユニーク。営業職員と直接話したい人は旧来の方法も選べるし、ウェブの中で完結することもできる。顧客にとって選択肢が広がっている。
若松 高齢化社会ということもあり、みんなデジタルがいいわけではない。ついていけない人はいるだろうし、働いている側にとってもソフトランディングが望ましい。そこで、今ある自分たちのアセットを使ってどう事業展開するかを考えました。
まず、営業職員のページが存在します。従来は、営業職員が最近の出来事など一言書いてコピーして、飴玉と一緒に顧客にお渡ししていました。それを単に電子化するだけでなく、プラスアルファとして、Aさんに届ける情報とBさんに届ける情報を変える。つまり、パーソナライズされた情報を提供できる。顧客は好きに見て、興味があったらレスポンスしてくれればいい。
高荷 第一生命保険さんの取り組みを見させていただいて、CX(カスタマー・エクスペリエンス)とEX(エンプロイー・エクスペリエンス)は、表裏一体だと感じました。両方を考えていかないと、新しいモデルは立ちゆかない。
宮田 新しい顧客体験を提供するためには、社内の働き方、従業員体験も当然変わっていかなければいけないし、EXもデジタル化し、データドリブンになっていくでしょう。CXとEXを両面で変えていくことが必要で、表面的なデザインなどをきれいにして終わりではない。そのためには今までフォーカスされていなかったところを企業として見直して、ケイパビリティに付け加えていかなければならない。
高荷 「顧客資本」という言葉の意味が拡張していますよね。そういう意味では、単純にリスト化されている顧客を資本としながらビジネスをつなぐのではなく、アノニマスの人たちも含めて見なければいけないし、従業員や直接的なステークホルダーも見ていかなければならない。
事業部がサイロ化し、顧客情報が活用できていない状況がDXを妨げる

中矢 そもそも顧客情報をまだ充分集めきれていない企業が多いことも課題です。顧客情報自体はどこかにはあるのかもしれないけど、実際には、契約情報や受注情報であったり、はたまたセットトップ・ボックスやメーターのような端末の情報だったり、それらをつなぎ寄せて人としての情報を作って活用することができていない。
高荷 何を買ってくれたかという購入履歴と、連絡先、電話、メールアドレスといった届けるための情報しかないんですよね。名寄せしても、この人がどういう人なのかわからない。人としての情報がない。
その点、美容室のカルテはよくできていて、どんな世間話したか、どんな気分や関心からどんなヘアスタイルを選んだかなど、全部書き起こしていますよね。要望と関心が詰まった顧客情報。まさに人としての情報です。
宮田 顧客からスタートしなければならないDXなのに、そのような状況が前提だとすべての企業がかなり大きなチェンジを迫られますね。
中矢 そうですね。BtoC企業でもBtoB企業でも、現場レベルではそうした変革のモチベーションを持たせづらいので、トップから「変わるんだ」という働きかけをすべきだと思います。それがうまくできている会社が多くないのも実態です。
宮田 なぜうまくできないのでしょうか。
中矢 事業部制が原因の一つとしてまず考えられます。日々のオペレーションが事業部というサイロで回っているため、その必要性を認識しにくいからです。自分たちのKPIは事業部内で完結しているから、他の事業と組み合わせたクロスセルにはならない。仮にそうしたくてもプライオリティが落ちてしまう。
宮田 うまくできている企業はどうしているんですか。そこでも事業部はあると思いますが。
中矢 関心が高い企業は事業部任せにせず、顧客情報を活用するミッションを持った組織や、担当の役員をしっかり付けて、その方が指揮を執っています。
組織に担当役員を設置せず、現場サイドでちょっと関心が高い人がなんとかやろうとしても難しい。というのも、顧客情報を提供する側と、それを受け取って利用する側がありますが、提供する側はその果実を得られないこともあります。そうすると、「自分たちにはメリットがないため顧客情報を渡しません」という話になってしまう。組織を横断して采配できる行司役が必要です。
宮田 顧客体験の変革を進めていくうえで非常に大事なのは顧客情報です。しかし、「顧客情報を活用したい」とトップが言っても、事業部に任せるとサイロ化してしまう。いかに全社的に事業部横断的に、または職能横断的に管理して、運営や活用をしていけるか。組織改革を含めてできるかどうかが、分水嶺ですね。
高田 データは企業の持ち物ではなく、人の心が動いて行動に移してくれた証拠という観点でも、生活者の持ち物だというのも欠かせない視点です。どういう前提で生活者からデータをお預かりするか、各事業部に任せてしまうとバラバラになってしまいます。専門の担当役員・部署を置いて、生活者から許諾を得るために、「対価としてこういうベネフィットを提供する」ということを、企業を代表して説明する責任もありますね。
高荷 誰もが顧客とのリレーションを深めたほうがいいと思っているけれど、今の事業機構が追いついていなければ、そのアイデアを推進できない。分業制によって、それぞれの利益を追求して全体益を失うことが起きてしまう。新しい潮流に対してフレキシブルにビジネス機構を変えていくことが、経営者のこれからのテーマでもあります。
宮田 さきほどの高荷さんの「生活者動向・DX 受容性調査」で、DXサービスの高度化の受容に対する態度保留層の理由の一つが、個人情報の管理でしたよね。
高荷 はい、そのとおりです。大きな理由は2つあり、1つ目は「使い勝手が悪く難しそうだ」というUX面で、2つ目が個人情報データの扱いに対する抵抗感でした。
また、個人情報譲渡の先の選定基準については「データ利用のルールが明示されている企業やお店」を選択した人が48%、ほぼ半数が許容できるとしています。「失敗をしない確信を持って、利用できる企業やお店」も44%なんですが、「ワクワクするような可能性を示してくれる企業」は、20%以下でした。
若松 「データ利用のルールが明示されている企業やお店」なら許容するといっても、そのルールをみんな見ているのか疑問です。
高田 実態としては、データを提供することによるベネフィットを理解しているような生活者は、見るにもおよばないので見ておらず、理解がおよんでいない生活者はルールを見るなど、いろいろなことを気にするというのが近いと思います。
高荷 そこも体験設計のポイントですね。今回の調査では、個人情報の認識についても尋ねました。「パソコンやスマートフォンなどでの個人情報やセキュリティの管理・設定についてどのようにしていますか」という質問では、43%が「定期的に設定を更新している」と回答しています。しかし、それをよくよく調べていくと「スマホやPCなどで定期的に求められるパスワードの更新」を「個人情報の管理」と思って誤回答している可能性があることがわかりました。
実は、生活者は何が個人情報なのかを明確に理解していない可能性があり、個人情報管理のリテラシーを私たちは低く見積もる必要があるんです。今は企業側も生活者側も暗中模索の中でお互いに手を出し合っている状態だから、全然グリップできていない。ただ、少なくとも暗い中でも手を差し伸べている人たちは、ちゃんと明示してくれなければ嫌だと言っている。これが今回の調査で初めてわかったことです。
企業側にはこうした新しいニーズに対応する機構作りや、顧客情報を得るためのリレーションの再構築が宿題として明確になっています。そういうことも含めて、IBMが提唱してきた「事業のリインベンション」を起こさなければならない。
顧客体験の戦略を事業戦略へつなげるために必要な、人間性重視のアプローチ

宮田 企業にとってやるべきことが積み上がってきていますね。その中で、企業は次世代の事業戦略や顧客戦略について、どういうことを踏まえて考えればいいか。何か示唆があればお伺いしていきたい。
高田 いま、さまざまな企業が顧客と直接つながり続ける仕組みの構築を急いでいますね。一方で、プラットフォームは似たようなビジネスモデルに陥りやすいという点に留意すべきです。自社の生業に留まらず、カスタマージャーニーに合わせて業態を変革しようとすると、金融機関であっても通信会社であっても目指す姿は同じ“人々の生活支援業”というところに行き着きがちです。
実際に、多くの経営者が5年後・10年後は、〇〇銀行・〇〇保険といった社名ではなくなっているだろうという主旨のビジョンを掲げられています。いよいよ企業のDXが本格化してきたと感じますが、ではどうやって同質化を避けるかが次の論点ですね。
クリエイティブをどうDXに取り込むかは一つのヒントになり得ると思います。例えば、今回の調査(「DXの加速による新商圏の誕生」「Withコロナ時代の成長戦略 顧客主導で推進する事業の再構成/リインベンションの実践」)の最終章には、2030年を予測した未来小説がありますよね。こういった新しい世界観を描くには、「こんな世の中にしたい」「こうだったらワクワクする」という主観が欠かせません。
生活者の観察や共感を通じた課題抽出という基本を抑えながら、どうやってそこにクリエイティブによるジャンプを組み込むかが、これからのDXに重要ではないでしょうか。
宮田 多くの企業が、生活基盤を支えるプラットフォーマーになりたいと考えている。だけど差別化要素が見出だせていないんですよね。プラットフォーム・ビジネスが一番強いと言われている中で、それを多くの企業がめざすのは論理的な帰着かもしれないですけど、ファーストステージが終わったように感じます。高田さんが言うように次のステージに行くには、新しいエクスペリエンスなり、顧客体験価値を提供するのかを考えなければいけない。我々もチャレンジではありますね。
高田 はい、そのうえでどうやって生活者に対する見方を変えてもらうかが次のチャレンジですね。生業を広げて生活者とつながるのは、企業視点では合理的ですが、それが生活者にとっても意味があるものかどうかは異なる次元の話です。新しいサービスを始めても、そこには既存の慣れ親しんだサービスが競合としてあるのが通常で、生活者が信頼し相談したいと思ってもらえる存在になるには放っておくと時間がとてもかかってしまいます。
ブランドのパーセプション変革が伴っていかないと、企業が目指す生活者に寄り添う存在になったり、体験を提供したりすることを実現していけないわけですから、こういった文脈でも、コミュニケーションやクリエイティブがDXの論点としてますます重要になると思います。
高荷 そうですね、新しい発想が必要です。社会とどうつながるか、事業とどうつながるか、未来とどうつながるかなど、顧客の関心が広がってきています。
その流れをキャッチするにはツールとしてではなく、シームレスに安心して顧客が社会や事業や未来とつながれる環境を作る必要があります。「シェルパ型」の体験設計と呼びますが、ユーザーに寄り添う環境をいかに作るのかが課題です。もしかしたら今後は音声デバイスによる会話が中核になり、会話で足りないものをテキストや動画で補うスタイルにとなるかもしれない。そうした人間性に配慮した次世代のビジネスモデルを、IBMとして「サービス・ヒューマン・インターフェース」と呼び、サービスという抽象概念の中にヒューマン・インターフェースを意識すべきだと提唱しています。
また、事業も顧客との一体化が進み、互いの価値を管理するための価値管理基盤をベースに、相互利益を積み重ねていくモデルに変わる必要があります。それができれば、企業はLTV(Life Time Value=顧客生涯価値)が高まり、安定収入を武器に投資も進められます。また、顧客はQOLの高まりが実感できるので、積極的にデータや心情も開示してくれるようになる。そういうリレーションモデルを作っていけるようになったらいいのではないでしょうか。
若松 その場合の価値管理基盤のオーナーは誰ですか。
高荷 相互です。企業側が提示する形で顧客が参加するコミュニティ・プラットフォームのようなものの進化版です。この形をどう作るのかが、これからの事業戦略上の大きな課題です。顧客リレーション戦略と事業戦略が一体になったモデルを作るわけです。
例えば、医師でありグラフィックアーティストでもある瀬尾(拡史)さんは、病院にある患者のデータを使って、3D空間にダミーを作るソフト「3DCG可視化システムViewtify®」を開発しました。心臓の疾患がある人は、その疾患がメタバースの中に再現されます。
宮田 人体デジタルツインということですか。
高荷 そうです。それをソニーの空間再現ディスプレイによって表示させるプロジェクトが行われています。これがなぜサービス・ヒューマン・インターフェースに当たるのかと言いますと、医師にとっては複雑に入り組んだ臓器をどう処置すればいいのか、3D表示よりもわかりやすくなり、専門的技術を発揮しやすくなります。一方、患者は正しくわかりやすく自分の状態を理解できますし、何が手術のリスクかも視覚的に知ることができます。相互理解が深まることで、医療がさらに大きくイノベーションを進められる可能性も出てきます。
宮田 病気の情報は究極的な個人情報。このデータがベースとなって、医師と患者の両方がメリットを得られる事業が成立するということですね。
高荷 そのとおりです。事業の位置付けやサービスの位置付けが大きく変わる事業となっているわけです。ビジネスにおいても、これくらいのリターンをきちんとデザインできるのかが大きなテーマになりますね。
IBMとしても、こういった動きを支援できるようにしていきたい。そのために顧客を魅了するアイデアを生み出さなければならないと思います。
高田 生活者にとって役に立つサービスを提供することでデータを集めることができ、データリッチになるから、さらにいいサービスが提供できるという循環が生まれる、まさに企業と生活者が共創する目指すべき姿ですね。
そのときに企業経営として何を指標として持つかも重要ですね。モノからコトへと業態変革を掲げながらも、従来どおりプロダクトの販売台数を経営計画に掲げ続けている。掲げなければならないケースもよくありますが、結局は売り切りで買ってくれる方が効率良いという思いが透けて見えるわけですから、これではスピード感のある変革はかなり難しい。生活者と関係を築いていく中で、どのように自分たちの価値が伝わっているかを指標として掲げるべきで、理想としては企業の経営指標と生活者が重要視することが合っている状態をまず目指すべきです。
宮田 顧客体験の戦略=事業戦略になっているので、それに合わせてビジネスのKPIを変えていかないといけないということですね。
今回の議論を総括してみます。顧客体験の設計は、デジタル接点とリアル接点を顧客が自由に選択できるストレスフリーなものへ進化していく必要があります。既存の顧客体験を見直し、新たな体験を提供しようとする先進事業も現れてきました。
企業が顧客体験変革による成長を実現していくためには大きく分けて3つの取組みが必要である。1つ目は自社の顧客情報の組織横断的な管理、2つ目は顧客に対する新たなベネフィットの提供、3つ目は顧客から見た自社のパーセプションの変容。顧客接点ではこれらを実現するとともに、並行して経営視点では、新たな顧客体験を支える従業員体験の設計や人材・スキルの育成、KPIの再設定も求められます。
IBMインタラクティブ・エクスペリエンス事業部では、顧客フロント領域におけるグローバル経営層や生活者への調査による深い知見と、お客様との変革の協業による多数の経験を有しており、事業成長を支える顧客戦略・顧客体験の策定から実現まで、お客様のパートナーとして、お客様とともに進んでまいります。

関連リンク
既存の顧客体験を見直し、新たな体験を提供していく共創パートナーであるIBM iXについては、こちらもご覧ください。




