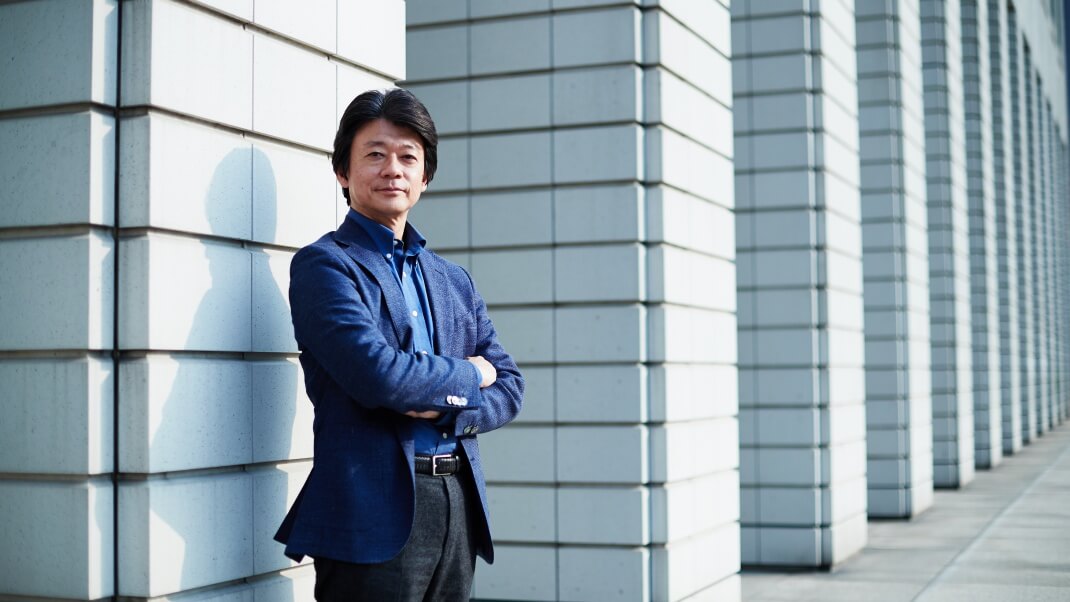東京大学と日本アイ・ビー・エム(以下、IBM)の協同による3年間のプログラム「Cognitive Designing Excellence(以下、CDE)」の2020年度第3回研究会が、10月7日に行われた。本プログラムは、人文社会科学系の学問と情報理工系の先端技術を融合し、社会課題を起点に従来にはなかった概念や社会モデルをデザインする研究プログラムとして2019年7月から始まった。2020年は、新型コロナウイルス感染防止のため、オンラインイベントとして開催している。
第1部のゲストスピーカーは、画家でありチベット難民孤児の支援を精力的に行っている藤田理麻氏。藤田氏はアメリカを拠点に活躍しており、現在はロサンゼルス在住。コロナ禍で移動がままならない中、オンラインだからこそ講演が可能になった。第2部では「食の偏在」と「相対的貧困」をテーマに、Zoomのブレイクアウトセッション機能を使い、少人数のグループに分かれて全員で討議を行った。
絵を描いて社会貢献することこそ画家の使命と気づいた特異な体験

第1部のゲストスピーカーである藤田理麻氏は東京で生まれ、15歳のときに父親の仕事の関係で渡米し、ニューヨークに32年間在住。その後、南カルフォルニアへ転居し10年目になるという。画業の傍ら、2001年からチベットの難民孤児たちに自身が制作した絵本を送ったり、教育支援をしたりするなど幅広い活動を精力的に行っている。
美大生時代から画家としてのキャリアをスタートさせ、ニューヨークでもトップの画商から高い評価を得ている藤田氏。しかし、以前は画商からだまされるといった嫌な経験も少なくなく、「けっして幸せではなかった」と語る。そんなある日、日本への一時帰国からニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港に戻った際、人生のターニングポイントとなる不思議な体験をしたという。
「そのとき私は熱を出してフラフラしていたんです。しかも家に着くまでに必要なドルを用意していなかったことに気付きました。空港は混雑して身動きもできない状態でした。すると急に目の前に一人の女性が現れて、私の手に何かを握らせたんです。なんだろうと見てみると、私がちょうど必要な額のドルだったのです。『嬉しいけどいただけません』とお断りすると、彼女は『あなたがとてもこれを必要としていたことを知っているので、どうか受け取ってね』と言う。内心嬉しかった私は、後でお金を返すために連絡先を聞こうと思い顔を上げたら、その女性はもうそこにはいませんでした」(藤田氏)
その数カ月後、自宅近くの書店で突然1冊の本が足元に落ちてきたという。手に取ってみると、それは駅や空港で困っているときに見知らぬ人に助けられ、お礼を言おうと思ったら、その人はいなかったという体験談集だった。
「胸がワーッと熱くなって、私は絵を描く意味が直感的にわかりました。それまで私は画家として有名になってお金持ちになることが成功でありゴールだと思っていました。なぜなら社会的にそう教えられてきたからです。『何が成功なのか』ということさえ考えたこともありませんでした。しかし、空港での出来事から、それまでゴールだった絵は単なるツールであり、絵を描くことで社会に貢献することこそが画家にとってのミッションだと気付いたのです」(藤田氏)
そして藤田氏は同時期に、夢の中で「チベットのためにできることをすぐにしなさい」という強い命令を聞き、チベット難民孤児たちの支援を始めたという。消えつつあるチベット文化やチベット語を守るための絵本、結核予防の本、女性をエンパワーメントする絵本、アイデンティティの絵本など7種類、計1万5000部以上を寄付。障碍を持つチベット難民孤児たちにも絵本やおむつ、パソコン、文房具などを贈り、ダライ・ラマ法王とも交流を深めている。
「ダライ・ラマ猊下からたくさん学んだことがあります。中でも一番深く心に残っているのは『すべては相互関係で成り立っていて、人はけっして一人では生きていけない。周りが苦しんでいる中、一人だけ幸せになることができない』ということでした。この考えを子どもの頃から教えられて育つチベット人は、どんなに貧乏でも困っている人を助ける思いやりの心を備えています」(藤田氏)
チベット難民孤児に会いに行ったときは、孤児たちが自分よりもずっとやさしく強かったので、自分が恥ずかしく感じるほどだったという。そして、チベット人たちは人と人とが支え合うだけでなく、動物や虫、植物、目の前に現れる生き物たちはすべて『前世で自分の家族だったかもしれない』と考え、縁があるものとして大切にするという。
内なるビジョンを描くことで、他者を思いやる心の大切さを伝える

藤田氏は「毎日、木と会話をしている」と語る。大好きな菩提樹の木に挨拶すると、何千枚もの葉が嬉しそうに動き出す。10年前からは動物の権利を守るためベジタリアンになり、今はヴィーガン(卵・乳製品も食べない完全菜食主義者)になった。形が悪いだけで市場に出ないという食材を取り寄せ、アメリカで40%と言われる「food waste(食料廃棄)」と、その腐敗により排出されるメタンの量を減らそうと行動している。
夢や瞑想で見たビジョンを絵にしているという藤田氏。毎年、東京・伊勢丹新宿店アートギャラリーで個展を開催し、2020年で27年目となる。
「今年のテーマは『思いやりの心』。新型コロナウイルスのせいで世界中が不安を感じています。私自身も3月から精神的に辛いことがありました。今なによりも大切なのは、自分へ、そして他者への思いやりの心ではないかと思います」と静かに語った。
講演後、参加者から「絵を描く目的が変わり、絵にも変化がありましたか」という質問があった。藤田氏は、「その前は外部の目で見たものを中心に描いていました。子どもの頃から時々、他の人には見えないものが見えることがありましたが、それを口に出して言うと『何を言ってるの』と言われていたものですから、そういう自分独自のビジョンを絵にすることはあまりいいことではないとずっと思い込んでいたんですね。でも不思議な体験を経て、内なるビジョンこそが私が描くべきものだと気付きました」と返答。
また、「絵を描きながら、内なる誰かと対話するようなことはありますか」という質問には、「実は、描いた後まったく覚えていないんです。誰かが私の中を通って、私を道具として絵を描いている感覚があって、“無”と言いますか、たぶんこういうのをトランス状態と言うのかなと思う」と明かしていた。
食の偏在と相対的貧困をテーマに、40年後の未来から今の課題を考える

次に「食の偏在」と「相対的貧困」をテーマにディスカッションが行われた。食料廃棄は、日本では年間612万トンと言われているが、これには形が悪いからという理由で生産過程において廃棄された10~15%は含まれていない。途上廃棄も含めると、実に合計1000万トン近い食料が捨てられているという。しかも、年間2兆円かかっている焼却費のうち約1兆円が食の廃棄費用で、多大な社会的コストがかかっている。
今回のテーマを提案したのは、内閣府による「スマートフードシステム」のモデルを構築するプロジェクトに関わっているキリンホールディングス株式会社 取締役常務執行役員の小林憲明氏。小林氏は、「2050年には世界人口が97億人になる。食料生産加工量をおよそ1.6倍にしなければ奪い合いになる。日本もお金を出せば食べられるという状況ではなくなる」と指摘する。
もう一つの問題として「相対的貧困家庭」を挙げている。日本では年収125万円以下の家庭を「相対的貧困家庭」としているが、コロナの影響もあって今後は収入が不安定な人がさらに増加すると見込まれている。だが、これは顕在化しづらい問題だという。
「解決がなぜ難しいか。食の偏在にしても相対的貧困にしても、習慣によるところが大きい。ルールとして賞味期限が決められていますが、新しいものから買っていくのは消費者の心理。けっしてルールではありません。加工食品は賞味期限が残り3分の1を超えると出荷できないというのも、ルールではなく商習慣。習慣は非常に変えにくい。気付きを提供しないと問題解決につながらない」(小林氏)
今回のディスカッションでは、各グループで40年後の2060年の未来像を描き、1)40年後の人から見たら、食の偏在と相対的貧困が起こっている今の世界をどう見るか。 2)40年後の人から今の姿をどう見られたいか(変えていきたい姿)。3)現在に生きる人が40年後の世界をどう見るか。4)食に係る「幸せ」とはどうとらえたか(量的補充ではなく、質的向上を考える)。この4つの個別検討軸を設けた。
ディスカッションはZoomのブレイクアウトルーム機能を利用し、出身地域別に7~8人ほどのグループに分けて40分間行う。その後、その結果を発表し合い、相互の視点の違いを感じ学び合う。グループのメンバー構成は、所属会社や組織、年齢層、性別はバラバラ。少人数でカメラをオンにすることで話しやすい雰囲気になっていた。「食」に関する話題だけに、食事を用意する母親の視点からの意見などもあり多様性に富んでいた。

「40年後の人から見たら今の世界をどう見るか」という点については、下記のような意見があった。
「今の世界は無駄が多い世界だが、気付きの世界にもなっているのではないか。『自己中心主義だな、余裕があったな、あの時代まで』と思われるかもしれない」(東北・北陸チーム)
「やはり飢餓があるのに食料を捨てているという矛盾がある。偏在を解決するAIやIoTという技術がそろってきている時代」(中部・甲信越チーム)
「未来をポジティブに見るか、課題があると見るか、二分した議論になった。40年後から見た今の世界は奪い合いの世界ではあるが、大きな戦争もなく活気のあるいい世界という面もある」(関西チーム)
「細分化、分断化が始まっている社会が今だと見られるのではないか。一方で、実は必要なエネルギーは摂れるし、必要な栄養素も技術のおかげで摂れる時代になったという意見が面白かった」(関東4チーム)
「40年後の人から今の姿をどう見られたいか」については、「飢餓、偏在を解決するアクションを取り始めた時代と言われたい。できたのにやらなかったと言われるのは辛い」(中部・甲信越チーム)、「せめて『我々の世代で少し何かやったよね』と思ってもらえるような行動が取れれば」(関東4チーム)という意見があった。
「40年後の世界をどう見るか」はこのままでは危機的な状況になると考えるチームが多かったようだ。
「このままいくと資本主義が終わり、地球も終わるだろう。よりよい未来は思いやり、足るを知る未来なのではないか」(東北・北陸グループ)
「人口の増加と気候変動によって食料が足りなくなって争奪戦が激化するだろう」(中部・甲信越チーム)
「今の世界が続くと、格差が進み、食費が高騰していくだろう。しかし、食料生産の技術が効率化されるというポジティブな一面もあると考えられる」(関西チーム)
「継続的に課題が解決されず、さらに地球温暖化や格差が拡大してしまう。状況が悪化すれば、最終的には人類が滅亡するのではないかということが熱く語られた」(関東1チーム)
「もしかしたら栄養はすべてサプリメントから摂り、美味しさはいらないという状況になるかもしれない」(関東2チーム)

「食に係る『幸せ』とはどうとらえたか」についてはさまざまだった。
「食の幸せは、好きなときに好きなものを食べられること。『突然あの店がなくなったのは、自分たちが行かなくなったからだ』『あの食材が食べられなくなったのは自分たちが環境を破壊したからだ』。そんな世界になる可能性もある。自分たちの幸せという観点と、社会の幸せは相反するところもあるのではないか。食の持続性を社会全体として作っていけるといい」(中国・九州・沖縄チーム)
「食の幸せは、利他の精神が個人の食の中にも根付いていくことだと思う。それが社会へ広がるといい」(関東1チーム)
「食べることには、美味しさや誰と場を囲むかという価値もあるはずなので、その価値を見直して食べることを楽しむ未来を作っていければいい」(関東2チーム)
「今後は肉ではなく代用肉バーガーや昆虫食なども出てくるだろう。フードロスについては教育やメディアによる周知が足りないのではないか。この知識不足をどういうふうに改善するのか。テクノロジーと知識で人の日々の行動を変えない限り、食料の遍在性はどうやっても解消されないと思う」(関東3チーム)
藤田氏はディスカッションについて、「これからの時代、本当の『幸せ』は何かという問いは、食べ物だけでなくすべてに影響すると思う。『利他主義』という言葉が他のグループからも出たが、やはり今までのような利己主義がベースの食のありかたは、今後はもう続いていけないと思う」と感想を語った。
テーマを提案した小林氏は、「当初この設定をしたときはネガティブな意見ばかりになるかと思いましたが、実際はそんなに悪くはないのではないか、改善されていることもたくさんあるという意見が出たことは大きな気付きでした」と語り、各チームの意見を参考にしていきたいと語った。
産学がスペキュラティブな方法で協同して、見えてくる社会課題

最後に総括として、東京大学大学院 情報学環・学際情報学府教授・Ph.D.の中尾彰宏氏は次のように述べた。
「東京大学は日本で初めて大学債(FSI債)を40年債として発行することになりました。これは大学において長期投資が可能になるということです。今回の「40年後」の未来社会を考えるというテーマ設定は、全てのステークホルダーが今後40年の長期投資をどう考えるかという視点が動機となっています。40年後の未来社会に向けた大学の社会的役割は、最先端の研究と人材育成だと思います。つまり、若者たちに生き残るための知恵を身につけてもらうことです。たとえば食の危機が来るのであれば、代用肉の話が出ましたが、これまでなかったものから食を作っていく発想の研究教育が必要。40年後の人材育成のために長期的な投資をしないとならない。それが大学の使命。私の専門である情報通信で言うと、これまでのペースで考えれば40年後には情報通信の容量が100万倍になります。もはや現実を超えて仮想世界の方が大きくなる。我々は技術が人知を超えるという意味で特異点(シンギュラリティ)と言っていますが、よく言われる『超知性』だけではなく、仮想世界が現実世界を超える『仮想集中』が起こるだろうと思います。そのような特異点を超えて対応できる人材を育成していかないといけない」(中尾氏)
東京大学 名誉教授で中央大学国際情報学部 教授の須藤修氏は、都市作りの面から食の危機を語った。
「今後のスーパーシティ、スマートシティは、農地も知的産業も、教育機関も持っているようなコンパクトなもの、食料もサーキュレートが容易に可能になるような都市群をいくつも作ることが必要なのではないか。ヨーロッパで最も大きい都市はロンドンの約800万人。パリが約500万人、ドイツは100万都市が最大規模。アメリカにしても一番大きいニューヨーク、ロサンゼルスで800万人くらい。ところが上海は約2200万人、東京は約1300万人(神奈川県、埼玉県、千葉県を加えた首都圏は約3500万人)、グレータージャカルタは約2400万人の巨大都市。エネルギーのロスも生じているし、食料の問題、仕事の問題も混乱している状況です。ITと食とエネルギーのありかたを考えて本当の意味でのスマート、賢い都市を作る。みなさん企業の方々には構想力もあるし影響力もあるわけですから、学生や我々研究者が協力し、次の方向を考えないといけないと思います」(須藤氏)
さらに、「このままいくと水資源が逼迫します。水資源をどうコントロールし、需要供給をするか戦略を立てない限り、地球はたいへんな状況に追い込まれるでしょう」とも指摘した。
40年後の未来を見立てるスペキュラティブデザインの手法を用いることで、さまざまな課題が浮き彫りになった。その課題を一つひとつどのように解決していくか。思考と行動を止めるわけにはいかないと感じさせる研究会となった。
「Cognitive Designing Excellence」では、東京大学が持つ人文社会科学系や先端科学系の卓越した知見と、IBMが持つAI、ブロックチェーン、IoT、量子コンピューターなどの先端デジタル技術を融合し、日本企業の強みを生かしながら持続的成長を実現する社会モデルの創出を産学連携で推進します。