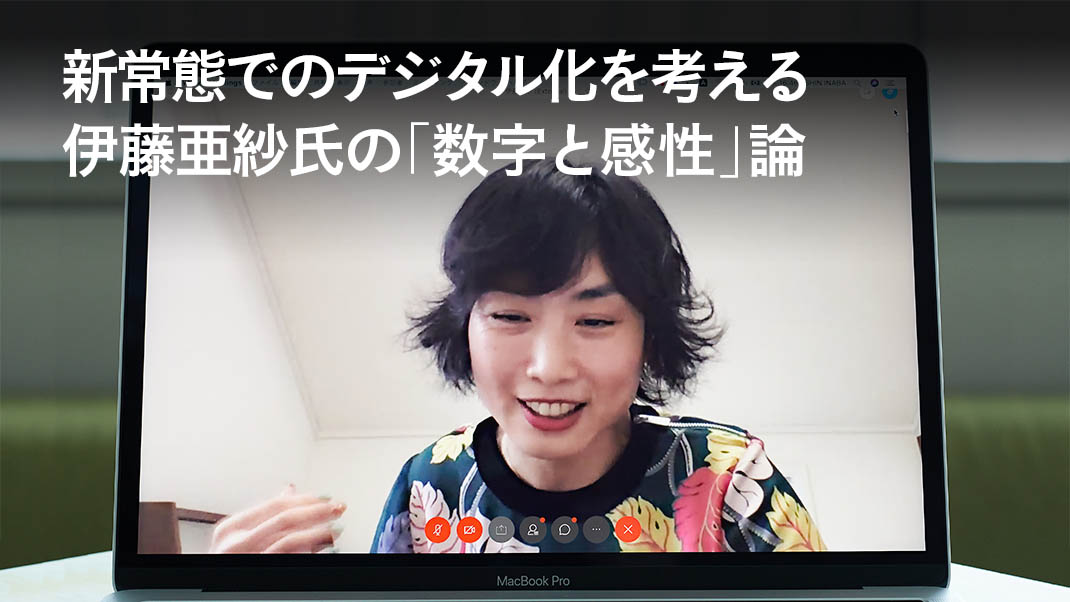東京大学と日本アイ・ビー・エム(以下、IBM)が協同し、人文社会科学系の学問と情報理工系の先端技術を融合して、社会課題を起点に、これまでにない概念や社会モデルをデザインするプログラム「Cognitive Designing Excellence(以下、CDE)」。2019年7月から始まった本プロジェクトは、3年間の予定で行われる。その第6回研究会が7月15日、前回に引き続きオンラインで開催された。
今回のテーマは「アフターコロナの新常態での働くことの意味」。新型コロナウイルス感染症(COVID-19/以下、新型コロナウイルス)の影響で働き方は大きく変わった。ニューノーマルの時代、「働く」ことはどのように変わっていくのか。まず第1部として、東京工業大学「未来の人類研究センター」のセンター長を務め、リベラルアーツ研究教育院准教授として美学・現代アートを研究する伊藤亜紗氏を招き、基調講演「数字と感性―労働について考えるヒント―」が行われた。
第2部では、「デジタル化は社員のためになるのか?」「在宅勤務へのシフトによって生まれた分散した労働環境の中で求められる自立的協働が有効に発揮できる『場』とは?」「イノベーションをリードする人財を引きつける場とは、企業は何ができるのか?」という3つの問題提起がなされ、CDE会員によるディスカッションが行われた。
美学が問いかける、明確に数値化することの是非

伊藤氏が専門とする美学は、言葉での表現が難しい身体の感覚などを言語化し深めていく学問。伊藤氏は障碍を持った人がどのように世界を感じているかについて研究を進めている。また、2020年2月に東工大にできた人文系の研究センター「未来の人類研究センター」では「利他」をテーマに掲げ、本当に人のためになるとはどういうことか、人を受け入れるスペースを作ることが利他的なのではないかと考え研究を進めている。
伊藤氏は、最近感動した料理本として、タレント・滝沢カレン氏の著書『カレンの台所』(サンクチュアリ出版)を紹介。
「料理が得意ではない人は、よく『作り方通りに作っているけどうまくいかない』とおっしゃる。大さじ3杯、30グラムなど、数字に従って作っているのにうまくいかない。しかし、料理は『大さじ3杯』と書いてあっても『今日の大根は水分が多そうだから大さじ3.5にしよう』など、食材から感じとったものを数字にのせていかないとおいしくならない。数値化できるものをさらに超える感性について考えさせられたのがこの本。数字は一切出てこない。たとえば、唐揚げの下味をつけるときは『お醤油とお酒を全員に気付かれるくらいの量』と書いてある。すなわち鶏肉たち全員が『お醤油とお酒が来た』と感じる量。食材に感情移入をした表現になっている。彼女は日本語の表現がヘンだと言われるが、彼女なりの感性を忠実に言語化した結果がこれだと思う。とても美学的な本だと思います」(伊藤氏)
経済学では、「数値」化されたインセンティブが良い行いの動機を減じてしまうのではないかという研究が行われているという。たとえば、小さい子どもに「お小遣いをあげる」という動機付けで料理のお手伝いを促進しようとしても続かない。料理をして楽しい、家族に喜んでもらってうれしいという内発的な動機のほうが継続する。逆に「罰金」の制度も、かえって望ましくない行動をする人を増やしてしまうケースもあるという。たとえば、ある託児所で時間通りに保護者が迎えにこない場合は罰金という制度を作ったところ、以前よりも遅刻する人が増えたそうだ。数値による制度を作ったことによって、「罰金を支払えば延長してくれる」という考え方に変わってしまい、その託児所と保護者の精神的な一体感がなくなってしまったのだ。
「安心」と「信頼」、「触る」と「触れる」から考える、ニューノーマルにおけるコミュニケーション

「そこで考えてみたいのが、安心と信頼という問題。私たちが数値化に走るときは安心がほしいとき。説明責任がつくということだと思います。しかし、安心と信頼という言葉は一見とても近いようですが、対立する概念と言われています」(伊藤氏)
たとえば、両親が心配してGPSを付け、行動を管理されている大学生。両親は安心を得られるが、大学生側から見たら「両親に信頼されていない」と思うのでないか、と伊藤氏は指摘する。
「安心は人を管理することにつながり、信頼は管理ではなくその人の自立を重視すること。信頼は相手がどういう行動をするかわからない不確実性が存在しているにもかかわらず、たぶん大丈夫だろうと賭けること。それに対して安心は社会的不確実性を最小限にし、相手と自分の関係の間に不確実なことが入らないようにしていく。結果的に相手を管理するということになる。テクノロジーを導入していくと安心を強化していきがちになり、結果的に信頼が失われてことがあるように思います」(伊藤氏)
視覚障碍者がランニングをするとき、両端が輪になったロープを伴走者とともに持ち、手の動きをシンクロさせながら走る。伊藤氏もアイマスクをつけてこれを体験した。初めのうちは伴走者を信じることができず、足元に段差があるのではないか、障害物があるのではないかと恐怖を感じたという。しかし、伴走者を疑うことを止めて100%信頼し身を委ねることにすると、「ここは注意」「ゆっくり行こう」など「伴走者の思っていることがロープを通して伝わってきた」。触覚的な人間関係、そこにある信頼の奥深さを実感したそうだ。
「ニューノーマルにおいて、触覚はキーワードになってくると思います。私たちはネットを使って会えるが、接触の機会、触覚の機会が圧倒的に減っている。手を使って触ることも失われていますし、象徴的な意味での接触も失われつつあるのではないか」(伊藤氏)
そこで、伊藤氏は「触る」と「触れる」の2つの触覚を表す語を紹介。「触る」は相手の感情を考えずに一方的に接触する。「触れる」は物質的な接触だけでなく感情的な交流を含める相互的な意味を持つ。そして、ネット回線を使った会話や会議は、「触れている感じがない」と言う。
「コミュニケーションは『伝達』であり、発信者の中にメッセージがあって、それを受信者の側に伝達すると考えられてきました。しかし、実際にはそのようには会話していないと思うのです。自分が伝えたいこととは違うところに相手が注目して解釈して答えを返してきて、それに会話が引っ張られることもある。会話はメッセージの発信/受信とは違って、お互いの関わりの中で生成していくもの。『触る』と『触れる』の違いに似ている。今のような状況下のバーチャル化したコミュニケーションの中でも、この2つを使い分けるようになるといいなと思いました」と結んだ。
みんなが参加できるデジタル革命。第一生命の取り組み

次にディスカッションが行われた。議題は3つあり、1つ目の問題提起は「デジタル化は社員のためになるのか?」。
チャットボットによる手続きやRPAによる省力化など、積極的にデジタル化に取り組んでいる第一生命執行役員の拝田恭一氏は次のように語った。
「現場の人がみんなで参加するデジタル化をめざしています。デジタル化は誰のためのものなのか。もちろんお客様だったり、会社の利益のためだったりしますが、現場で働いている人がどう感じているかが重要なポイント。人でなくていい仕事はロボットやAIに代えていき、人はお客様へのサービスなどリアルの価値をどうやって高めていくか。デジタルとリアルのサービスを組み合わせ、カスタマーエクスペリエンスをいかに高められるかがこれからの課題になっていく」(拝田氏)
これに対して、「デジタル化によって自分の会社の中の社員が便利になるようにするだけでなく、企業間、業界間、全部をつなげる形で考えないと、社内で収まっている以上はたいした進展にならない。全体的に実行していかないと前に進まない」「建設業は、伊藤先生が紹介した滝沢カレン氏の料理本のように、感覚で身につけ、体得して覚えなければいけないことも多い。デジタルで数値化してしまうと、それが継承されなくなってしまう。その点に多少問題を感じる」といった意見があった。
教育現場の試行錯誤から探る、リモートワークにおける信頼の作り方

2つ目の問題提起は「在宅勤務へのシフトによって生まれた分散した労働環境の中で求められる自立的協働が有効に発揮できる『場』とは?」。
まず、第一生命執行役員の重本和之氏から同社のESG投資の基本方針について説明があり、「革新的なイノベーションの創出に向け、成長企業・ベンチャー企業への投資(インパクト投資)を拡大していきたい」「社会的インパクトのモニタリング手法を確立し情報開示を強化、我々の運用ポートフォリオのCO2排出量や投融資を通じたポジティブ・インパクトの創出量について社外に開示していきたい」と語った。投資家は企業のESGを厳しく見ており、QOL向上、気候変動の緩和、地方創生などイノベーション創出などを重視していることがわかった。
そうした流れの中で、新型コロナウイルスが発生。リモートワークが短期間のうちに一気に進んだ。オフィスではなくリモートで仕事を行う上では、誰かに監視されなくても個が自立的に仕事を行い、自発的に成果をあげ、他者とコラボレーションして信頼関係を作っていかなければならない。こうしたときに必要な「場」はどのようなものなのだろうか。
この問題を考える上での一つのヒントとして、女性誌『日経ウーマン』(日経BP)による2020年「女性が活躍する会社ベスト100」で1位となった日本IBMの例が挙げられた。IBMでは、女性活躍だけでなく人種差別問題にも長きにわたり取り組んでいる。米国政府が機会均等法を打ち出す約30年前の1899年に、IBMの前身となる会社は雇用機会均等を発表。この根底にあるのは、イノベーションを生み続けるためには多様性が必要であり、また、社員全員がプロフェッショナルで、アントレプレナーシップを持たなければならないという理念だ。評価方法も独特で、昇進したい人が自ら手を挙げ、スキルレベルが達していれば昇進できるという。
「社員が自立するには、安心して仕事できることが大事。会社にとって安心となるのは数字管理だと思う。ただ、数字管理以外の方法で、社員が自立的でありながら組織と信頼関係を作るにはどうすればいいか」とIBM CDE統括エグゼクティブの的場大輔氏が問いかけた。
伊藤氏は次のように語った。
「教育の現場だと学生を時間で見ていくことが大事。『アトリエ環境』という考え方がある。美術のデッサンでは中央にモデルがいてその周りで全員がデッサンする。お互いの進捗を言葉には出さないが、横目で感じ取りながら作品を作っていく。これは教育的な効果が大きいと言われていて、最初から完成までを開示していくことで、途中で『これは違うのではないか』ということが起こっても、その瞬間的な判断だけでなく、どちらに向かっているのか方向性を見てあげることができる。そこが信頼につながっていく。オンライン講義においては、授業専用のInstagramを作り、学生が課題を制作する上で『こういうことを考えた』『こういう実験をした』とプロセスを共有している。場は共有できないけど時間は共有できるような工夫をしています」(伊藤氏)
これに対して、「リモートワークでのマネジメントは1on1を中心に行っていたが、部下同士、お互いの共有化が欠けていたことに気付いた。参考になった」という意見や、「バーチャルオフィスで自分のアバターを飛ばしても、隣が本当に何をしているかアバターだとわからない。難しい」という意見があった。
伊藤氏は「リモートでコミュニケーションをするときに大事なのは方法を1つにしないこと。大学でオンライン講義をするときは、Zoomで学生に話しかけつつ、チャットを使って情報を送りあったり、さらにInstagramを活用したり、さまざまな流れを融合して場を作り出そうとしている。そうして複数化することで学生の使いやすいように使いこなすことができる。場を作ろうとして1つの方法に負荷をかけてしまうと、それに参加している人の自立性や能動性が失われ、そのフォーマットに支配されてしまうような気がする」と自らの体験からデジタルにおける「場」の作り方のヒントを示した。
イノベーション人財を引きつけるため、組織や人を変えるオリンパス

3つ目の問題提起は「イノベーションをリードする人財を引きつける場とは、企業は何ができるのか?」。
まず、オリンパスの医療機器開発について同社執行役員の長谷川晃氏が説明を行った。消化器内視鏡において世界で約70%のシェアを誇るオリンパスでは、2019年から職務型(ジョブ型)の人事制度に転換。医療機器の領域で社会価値を生み出すには、グローバルにさまざまな専門家が必要となるため、各ポジションにおけるジョブディスクリプションを明確化して、適所適材の考えを実践している。この動きについて来られない社員もフォローしつつ、「専門性を持った技術的な人が共存するためには場、エンゲージメントが必要。なんのために協働するのか明確にしていかないと難しい」と語った。また、オリンパスのR&Dでは、一方の軸としてビジネス志向と技術志向、もう一方の軸としてイノベーション志向とオペレーション志向と、人材をタイプ別に分類。今後、イノベーションをリードする人材を引きつける場作りを探っているところだと言う。
CDE担当の客員研究員・嶋田文氏は、個の自由とセーフティーネットについての研究から、ニューノーマルでの場作りについて語った。嶋田氏によれば、「1000人の働き方を変えさせたいと思ったときに説明しても抵抗勢力がある。しかし、新型コロナウイルスによる不安、ニューノーマルにおける存在意義の不安という痛みを感じたことで考えが変わる。働き方が変わることでマイノリティーや不利が生じるが、インクルージョンを作ること、セーフティーネットとして受け皿となる評価やつながりを施策に落とし込むことが必要」という。
伊藤氏は「変わることの痛み」について、「人を変えることは暴力的なこと。間違えるとハラスメントになる。しかし、教育的な効果はその人に一歩踏み込まないとできない。学生の場合、恥ずかしい思いをすることも一つの方法。一回恥ずかしい思いをすると、その後はどんなことも言える関係になる。たとえば授業で絵を描くという恥ずかしい経験を講義の最初の段階で行う。そこで武装解除してしまうと、そこからの変化は起きやすいと思います」と教育的な観点から語った。
デジタル化には「自己家畜化」につながる危険性も潜む

総括として、東京大学名誉教授の原島 博氏は次のように警鐘を鳴らした。
「デジタルはアフターコロナの救世主になるか。もしかしたら逆かもしれない。伊藤さんには『ニューノーマルで失われるかもしれないものは何かを考える』という視点があると思う。デジタルは便利だが、便利だから人が幸せになるのかどうかは難しい問題。新幹線ができた時は、それまで1泊しなければならない大阪出張が日帰りでできるようになり、便利だし、1日時間が余って楽になる、クリエイティブな活動に当てられると思った。しかし、実際にはそうではなかった。競争社会ではライバル会社が翌日仕事をしていたら自分の会社もしなければならない。便利になると、それを大前提とした社会システムができる。いい悪いは別として、できあがった社会システムに縛られることになる。また、便利になると、いろいろなものを効率的に管理しようとする社会が必ず出てくる。人も管理された存在になり、さらに言うと管理された中でしか生きられなくなってしまう危険性がある。人類学用語でいうと『自己家畜化』、管理された中で家畜のように生きていかなければならず、場合によってはそれが快適だと思うようになる。管理社会が未来永劫続くならいいかもしれないが、東日本大震災や新型コロナウイルスで意外と脆弱だとわかった。便利な社会システムは必ずしも完璧ではない。アフターコロナにおいて、移動できない、直接会えない、だからデジタルだと結びつけるのは大丈夫だろうかと思っています」(原島氏)
東京大学大学院情報学環 学際情報学府教授であり、東京大学総長特任補佐の中尾彰宏氏は、新型コロナウイルスが拡大する状況において、東大では、移動通信業者による空間統計データ提供と連携し、匿名性を担保した上でネットワークを使ったキャンパス内の学生・教職員の行動を把握し、リアルタイムで人口密集地域を提示する「3密センサー」の実験を行っていると紹介。
「伊藤先生のお話にあったように、安心をめざしすぎると、管理や、さらにはシャットダウンにつながる。デジタル技術を駆使して行動変容を制御しながら、経済活動、研究活動を継続させることが重要。新型コロナウイルスが拡大する状況でも、技術を使ってイノベーションをリードしていく人材が必要です」と語った。
100年に1度と言われるパンデミックの危機の中、誰も正解がわからない中でどう生きるべきか模索を続けることになる。ただ、CDEのような場でさまざまな業界の企業と研究機関が手を結び、こうしてディスカッションしていくことはとても意義あることだと言えるだろう。
東京大学と日本IBMが、先端デジタル技術と人文社会科学を融合した社会モデル創出のために連携